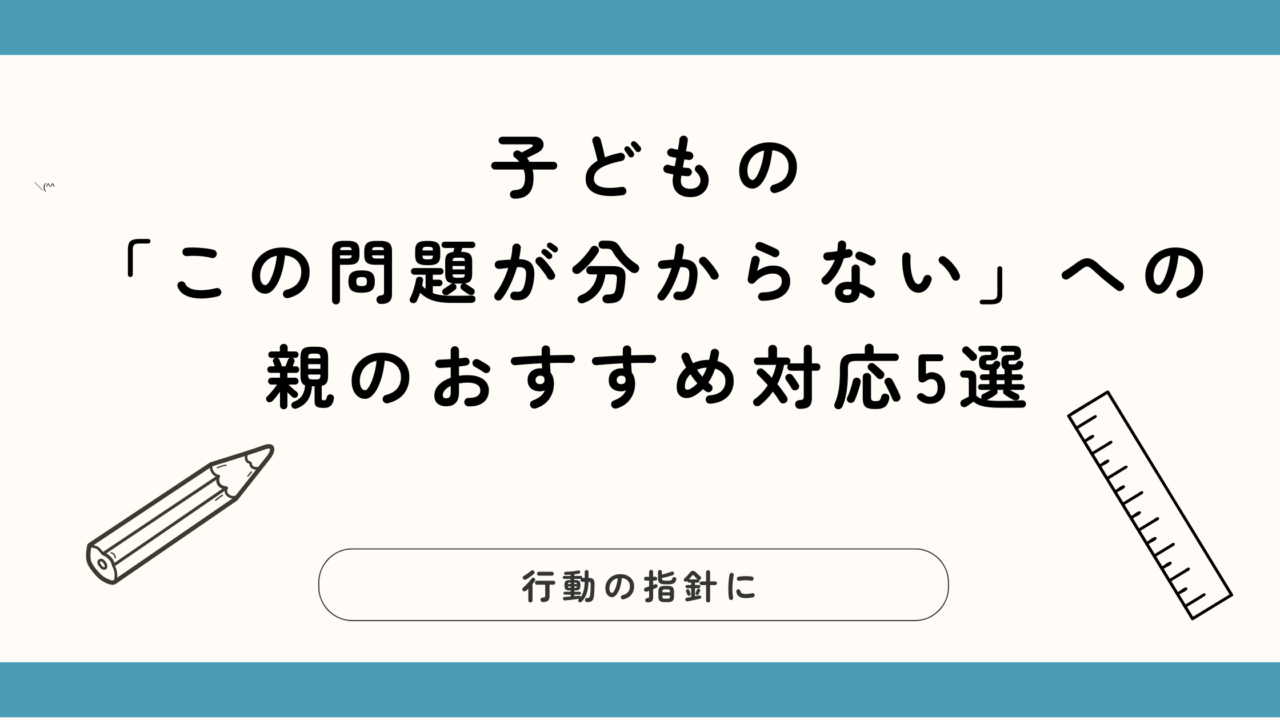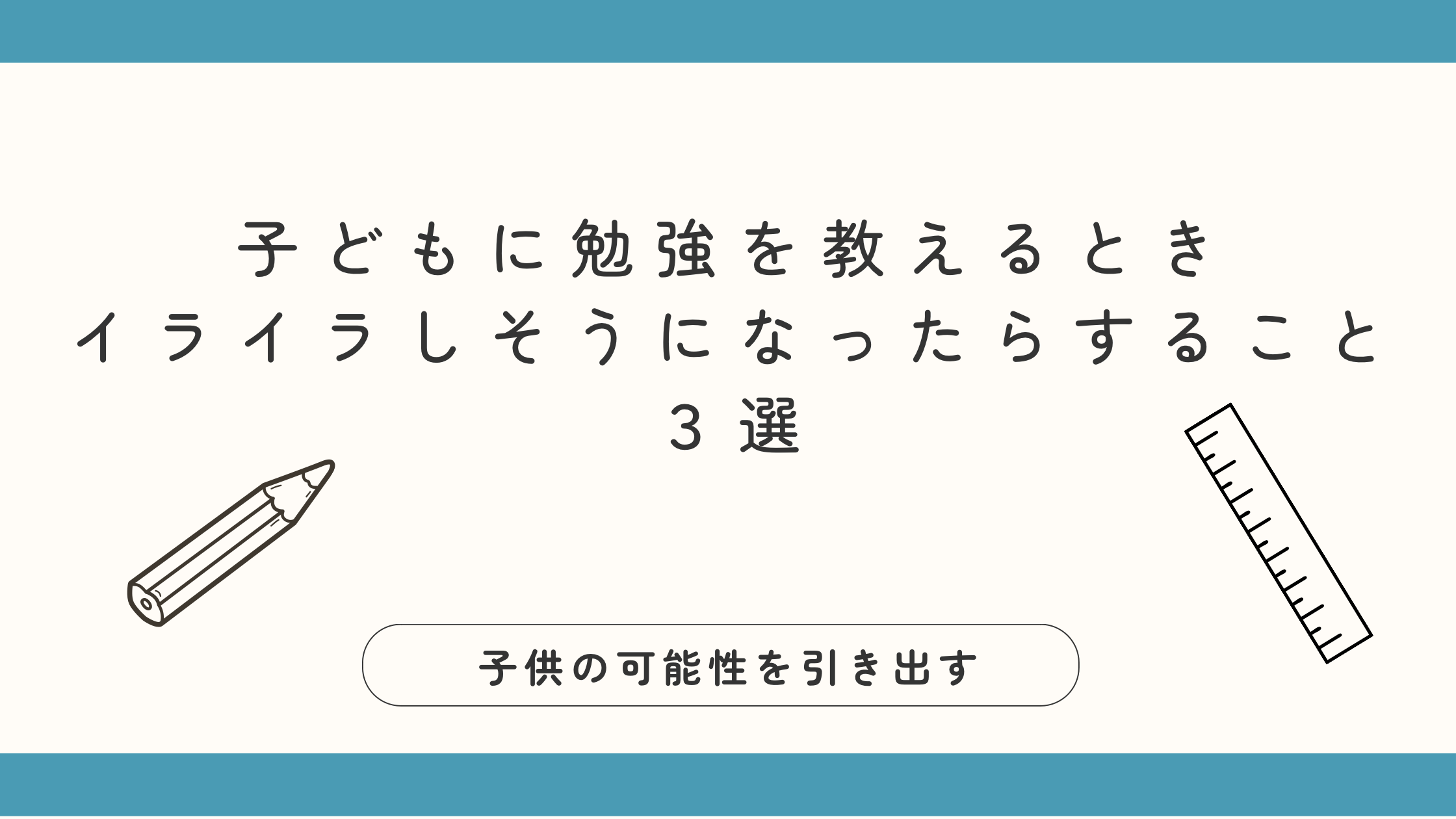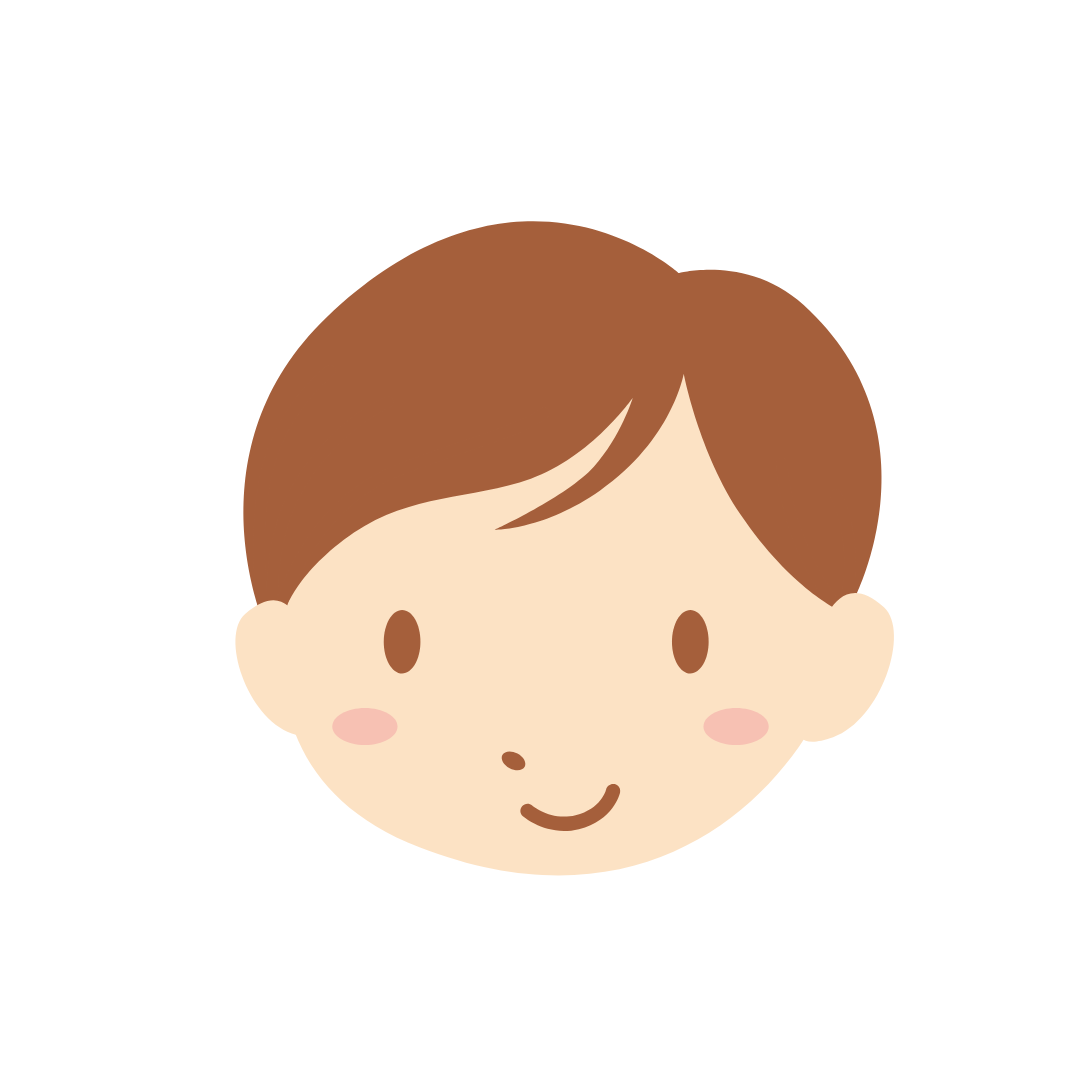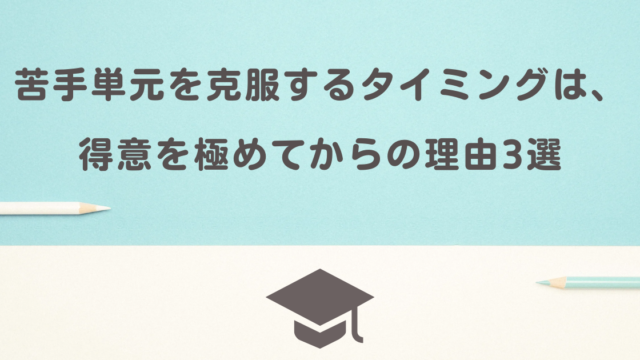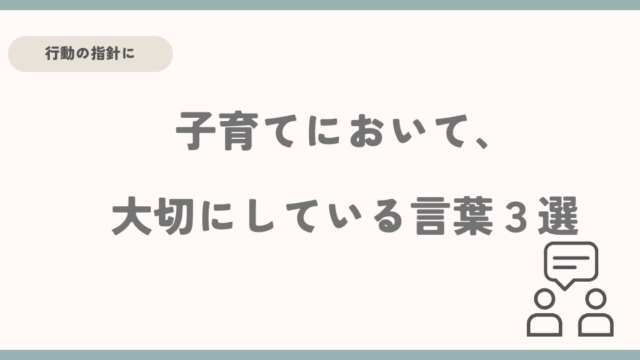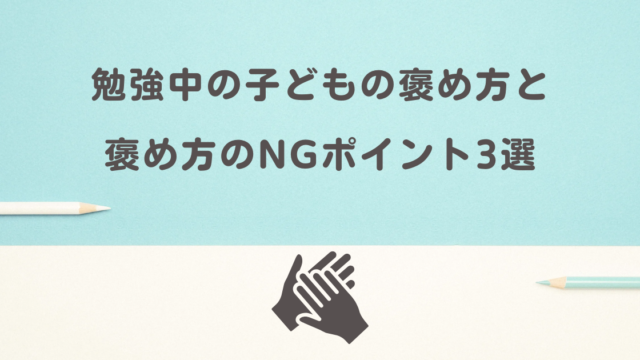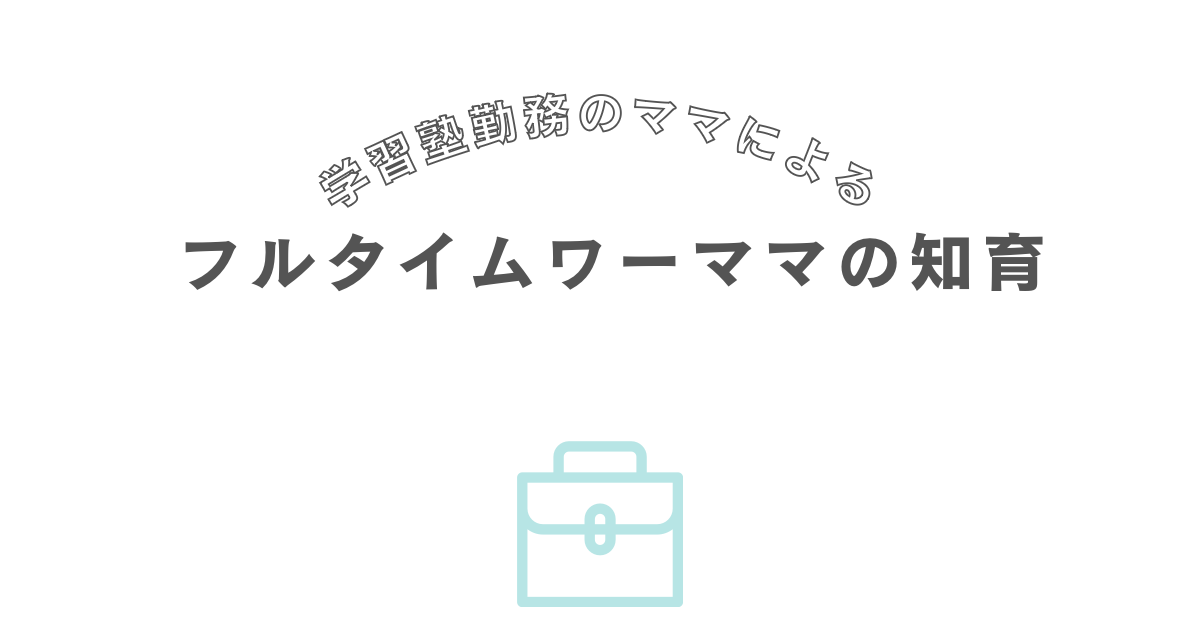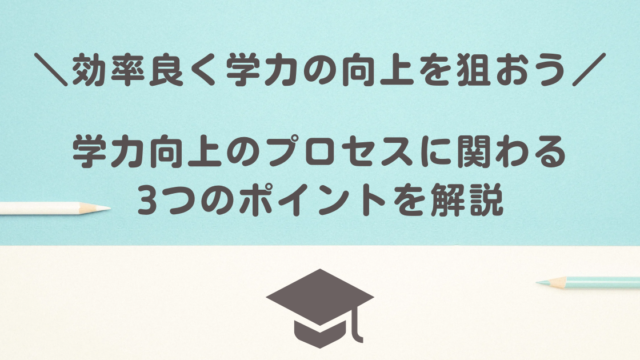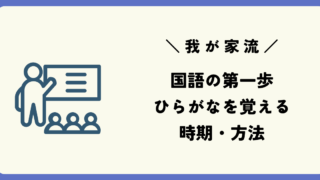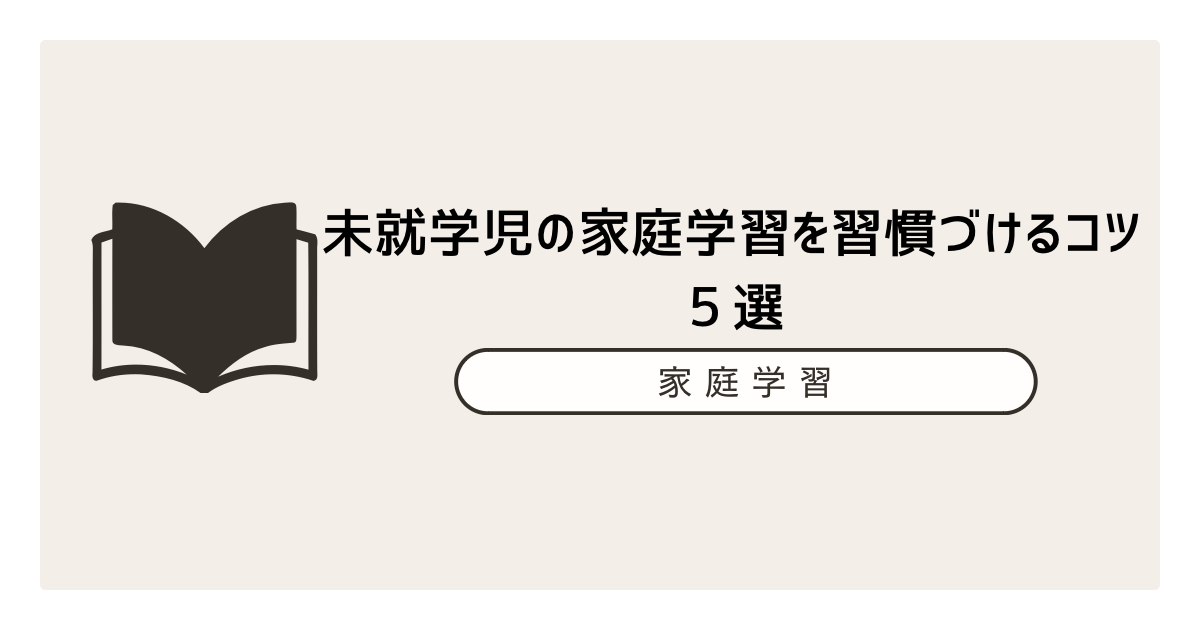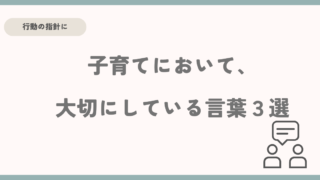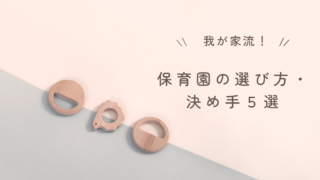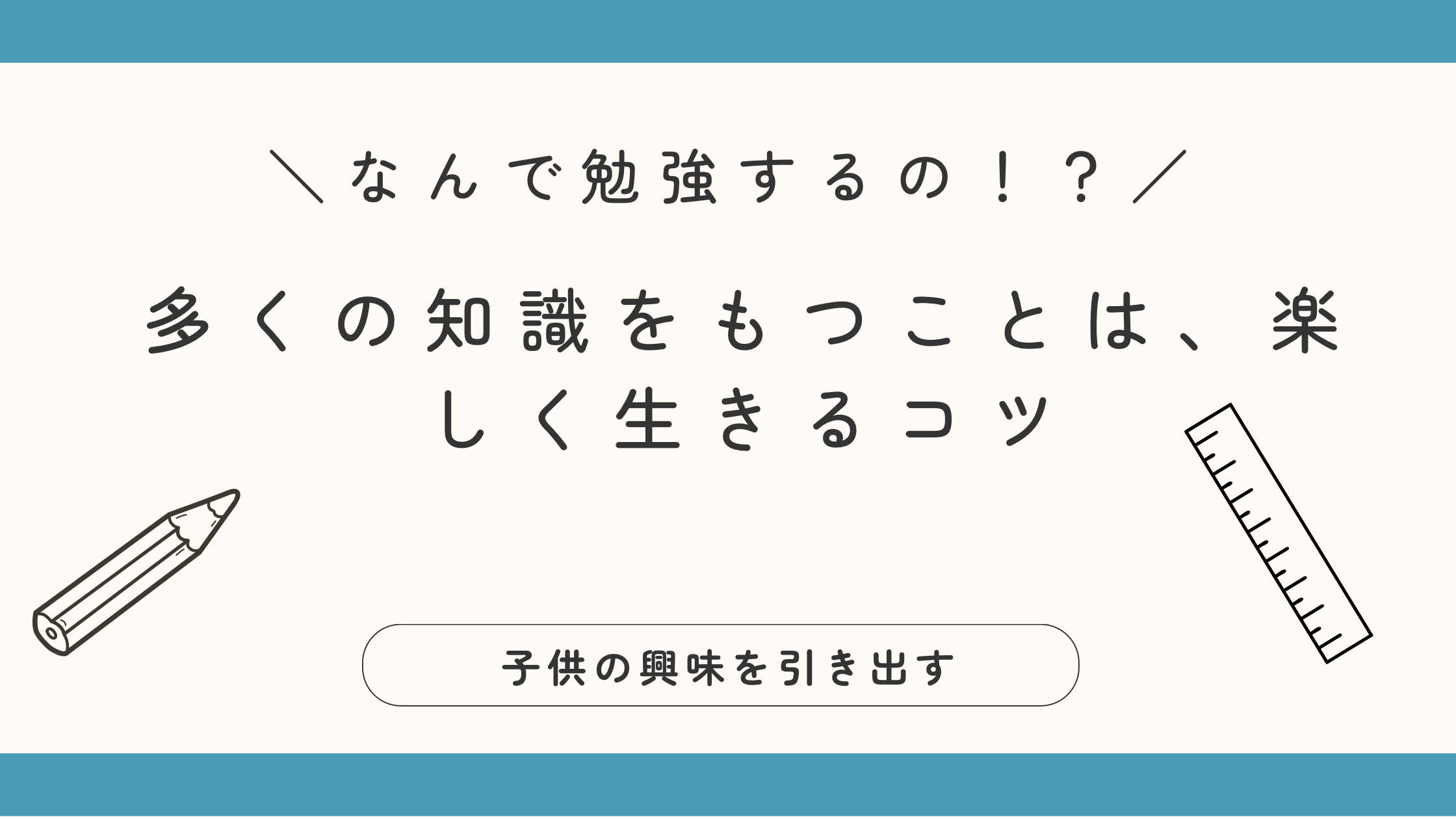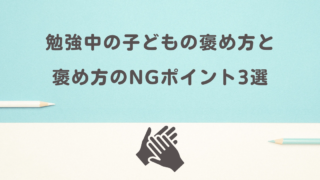よくある親御さんのお悩みです。
子どもの勉強の質問に上手に答えられません。子どもが「分からない」と言っていることもよく理解できず、結局イライラして、つい喧嘩になってしまいます。
子どもが勉強をしているときや、親が子どもの勉強を教えたり見ていたりしているときに直面する問題の一つに、
子どもが「問題や単元を理解できない」ということが、よくあるのではないでしょうか。
子どもが1回「分からない!!」となると、イライラしたり、全てが投げやりになってしまったり、
親御さんまでイライラしたり、教えてるのに!ときぃー(>_<)となってしまうことがよくあるかと思います。
本日は、子どもが「分からない」となったときに、親の対応方法を紹介していきます。
親御さんのイライラを防止する心の持ちようをこちらの記事で紹介しています。
合わせて参考になることがあれば嬉しいです。
子どもの「この問題が分からない!」の対応
焦らずに待つ。いつか必ず理解できる時がくる。
一番の対応方法は「焦らずに待つ」です。
なんかもっと一瞬で解決しそうな、魔法のような方法がないのかと思うかもしれませんが、
「待つ」という行為が一番有効だと個人的には思っています。
特に幼児教育に力を入れていたり、中学受験を考えている親御さんは、お子さんに先取り学習をしていることが多いかと思います。
学習指導要領はよくできてきて、その学年の子どもの発達段階で理解できる単元で構成されています。
そのため、先取り学習で本来の学習時期より早い段階で勉強しています。
理解できない問題や単元があって当然です。
お子さんの得意不得意な分野によって、
何度説明してもなかなか理解できない分野があることも十分に考えられます。
親御さんも何度説明しても、なかなか理解できないとイライラが増すこともあるかと思いますが、
心配ありません!!
今はまだこの問題を理解できる発達段階にないだけ。いつか理解できる!!
と大きく構えていれば大丈夫です。
我が子の話になりますが、3歳頃、点つなぎの問題が上手にできず大号泣。
また今度でいいんじゃない!?と言っても、「今やるの!!!」と怒りながら、泣きながらやっていました。
しかし、4歳になったら泣きながらやっていた点つなぎはケロッとできていました。
点つなぎは我が子の能力では、3歳では難易度の高いものでしたが、
4歳では年相応の難易度になっていた、ということです。
子どもって、親が「もうやらなくていいよ」って言うと「やるーー怒怒」ってなりますよね。あれ、なんでなんですかね!?
いつか必ず理解できる時期がきます。
様々な角度から、何度も同じ解説をする。
子どもの理解できたポイントは様々です。
ある問題や単元を解説して、お子さんがあまり理解していない様子だったら、
別の角度から解説の方法を変えてみてもいいかもしれません。
我が子の例で説明します。
我が子は5歳の時、「ちゃ」「ちゅ」「ちょ」のような小さい文字の「拗音」(読み:ようおん)がなかなか書けるようになりませんでした。
「きゅうしょく」と書こうとしても分からず
「き」の次は「や」?「ゆ?」何??
のようにちんぷんかんぷんで、
私的には、我が子の理解の進み方的にはそろそろ拗音を書けるようになってもいいはずなのになぁ~と思っていました。
解説方法として、まずは、「きゃ」をゆっくり読みながら、「き」と「や」で二つに分けるように教えてみました。
しかし我が子的にはしっくりこなかったのか、
じゃあ「ちゃ」は?「ち」と何の文字?と聞いても
???
みたいな感じになり、あまり正答率は上がりませんでした。
しばらくこの方法で試しましたが、いまいち効果は見られませんでした。
次に、「きゃ」は「きゃ・きゅ・きょ」の一番上。
小さい文字は「や・ゆ・よ」から成り立ってるから、「や・ゆ・よの一番目は?」と質問して答えに導く解説方法にしました。
最初の反応はやはり??という感じで、次の教え方を模索していました。
その次は、「あいおうえお表を丸暗記作戦」です。
拗音が出てくるたびに、あいうえお表を出しお目当ての文字を見つけたら、その周辺の文字もついでに聞いてみるということをしましたが、
子どもに嫌がられてあっけなく断念。
他にもいい方法ないかなぁ~と思っていたところ、
2番目に試した「や・ゆ・よの何番目?」の質問がどんどん理解できるようになっていました。
「しゅ」は「しょ・しゅ・しょ」の2番目だから「や・ゆ・よ」のだから2番目の「ゆ」だ!
と自分で考えながら解けるようになっていました。
我が子には、この教え方が合っていましたが、別の5歳児には別の教え方がしっくりくるかもしれません。
それは、説明してみないと分からないところがあるため、まずは様々な角度から切り込んで説明してみることがオススメです。
そして、解説内容の反応があまり良くなくても、何回かは同じ説明を繰り返します。
我が子のように、最初は理解しにくかったとしても、後からじわじわ効いてくることがあります。
これは未就学児に関わらず、中学生の子でも本当にあるあるです。
日常生活と結び付けて教える
日常生活の中に勉強内容を入れていくことは超オススメです。
先日、我が子(5歳)が「給食、3分の2食べた」と言っていました。
おそらく保育園の先生の話を聞いていたのでしょうね。
「3分の2って何か知ってるの?」と聞くと、知らない、と。
そこから私の説明に火がついてしまいました(笑)
まずは全体を1として考えるよ。2分の1っていうのは2つに分けた1つ分って意味で…(以下省略)
上記の説明を、ケーキのおもちゃを用いて説明しました。
その後、家族でピザを食べたときに我が子が
あ!これ2分の1だ!!
と気付き、そこから4分の1、8分の1の説明や8分の2と4分の1が同じ説明ができました。
このように、普段の子どもの疑問や発言を聞き逃さず、勉強内容とリンクしていることがあればすかさず説明すると
勉強と日常生活が結びつき、子どもの中で勉強がさらに役立つものという認識が高まると思います。
このときの注意点としては以下の通り。
- 子どもに無理強いはしないこと
- 覚えているかどうかのテストしないこと
- 気分じゃないときは説明を切り上げること
親御さんが必死になりすぎて、子どもが乗り気ではないのに超長い説明をしたり、テストしたりすると、
子どもは内心「聞くんじゃなかった…」と後悔し、親への質問を段々としなくなり学習機会を損失してしまう可能性があるからです。
もちろん私を含めた世の中のお母さん(お父さん)、頑張ってしないようにしましょう。肝に銘じます。。。
その単元の動画を見せ、教える
親が上手に説明できない分野や単元はあると思います。私も正直たくさんあります。
そんな時は動画に頼るのもいいと思います。
今はYouTubeになんでもアップされている便利な時代となりました。
「分数 解説」と検索すると、良質な説明動画が数多く出てきます。
動画1本10分もない動画ですと、気軽に見れます。
動画やYouTubeに抵抗のある親御さんは、親御さんと一緒に視聴すれば大丈夫です。
視聴後に感想を言い合ったり、補足説明を入れたりすると、お子さんにとっても楽しい時間になるのではないでしょうか。
我が家では、理科の実験系などは動画で見ることが多いです。
これらは、言葉で説明するよりも実際の場面や現象を動画で見せた方が、理解が深まります。
まとめ
以上、私が経験から基づき実践していることを紹介しました。
子どもとの勉強時間が楽しい時間になりますように。
また、子どもが少しでも多くのことを学んで楽しい生活をおくれますように。