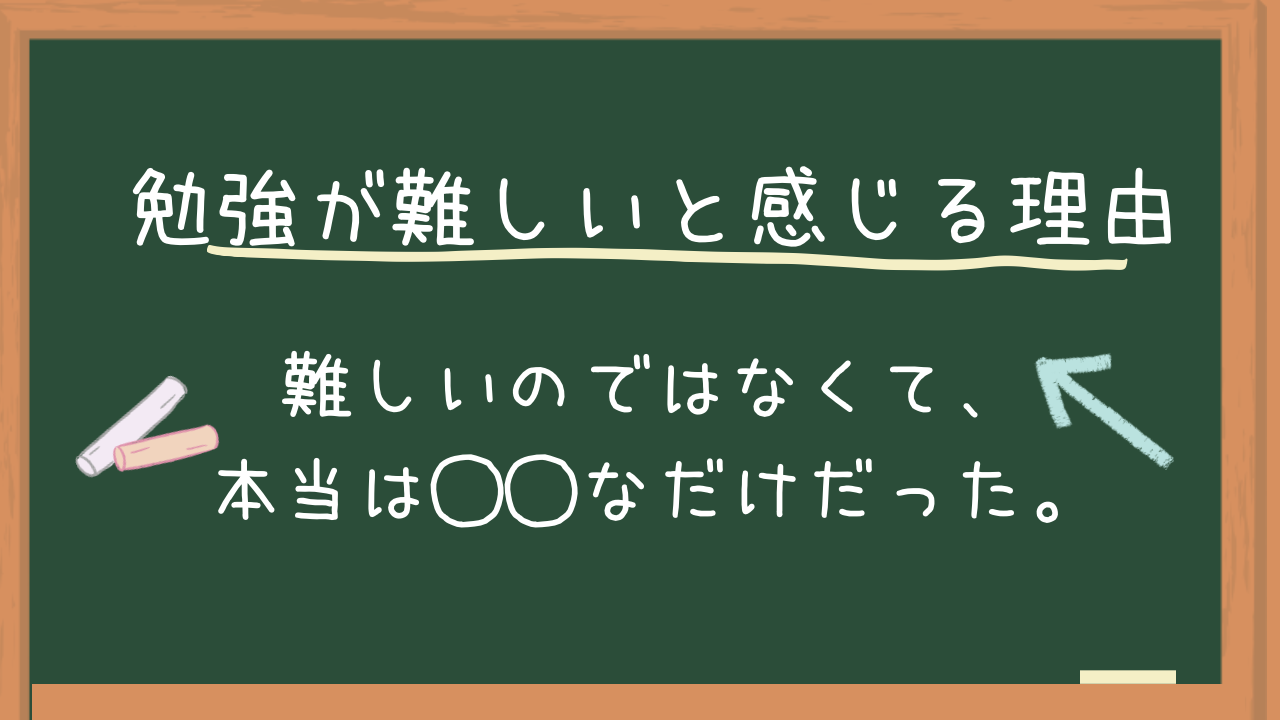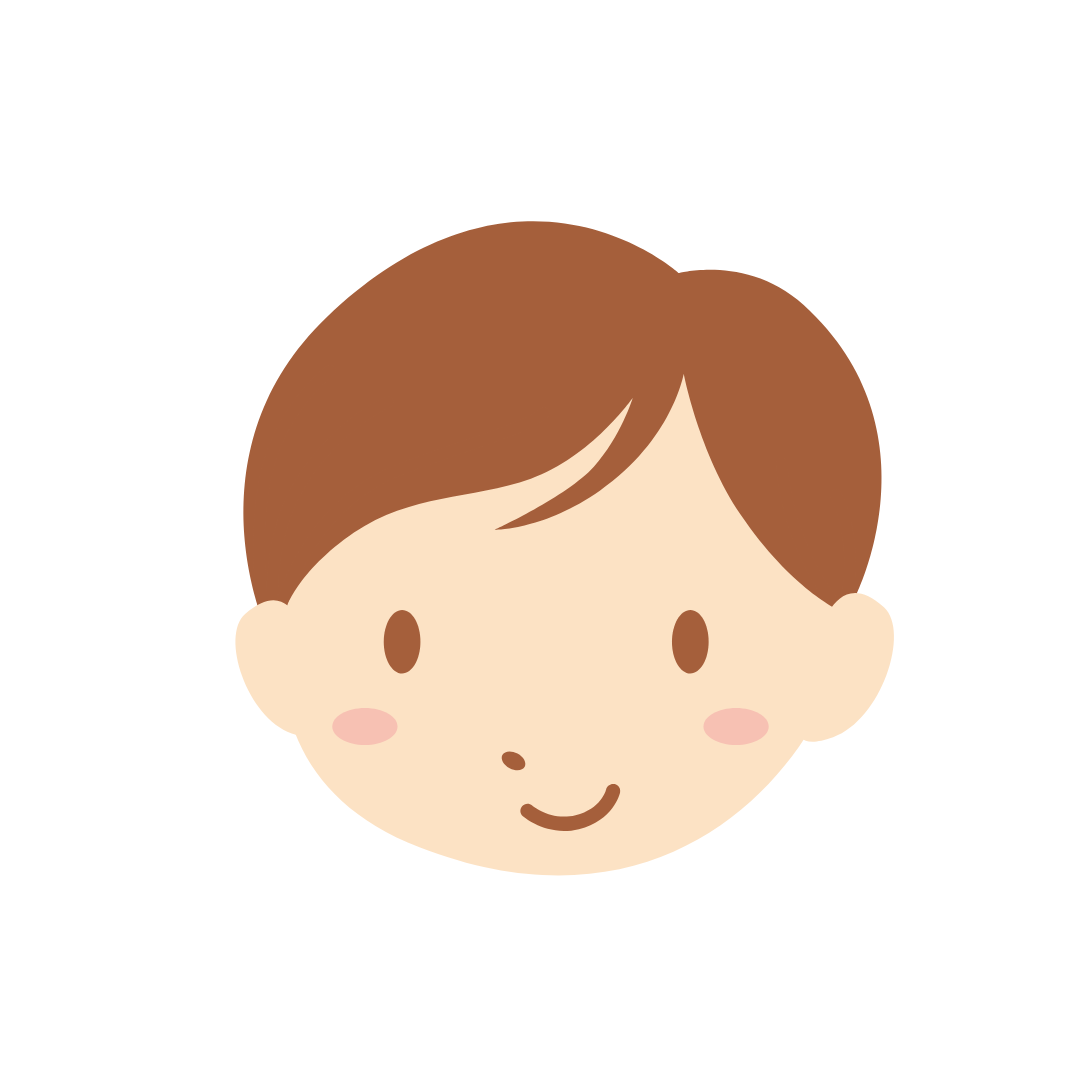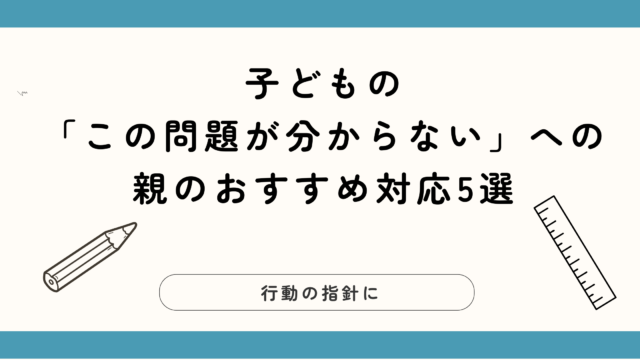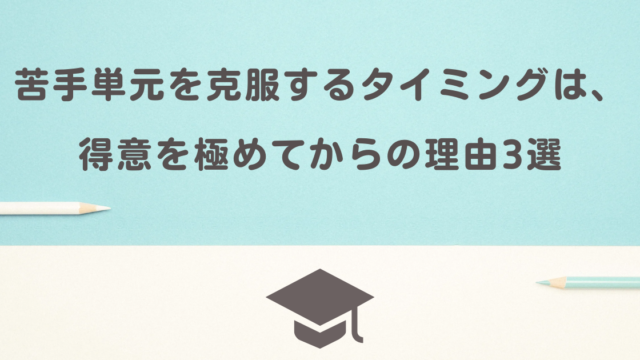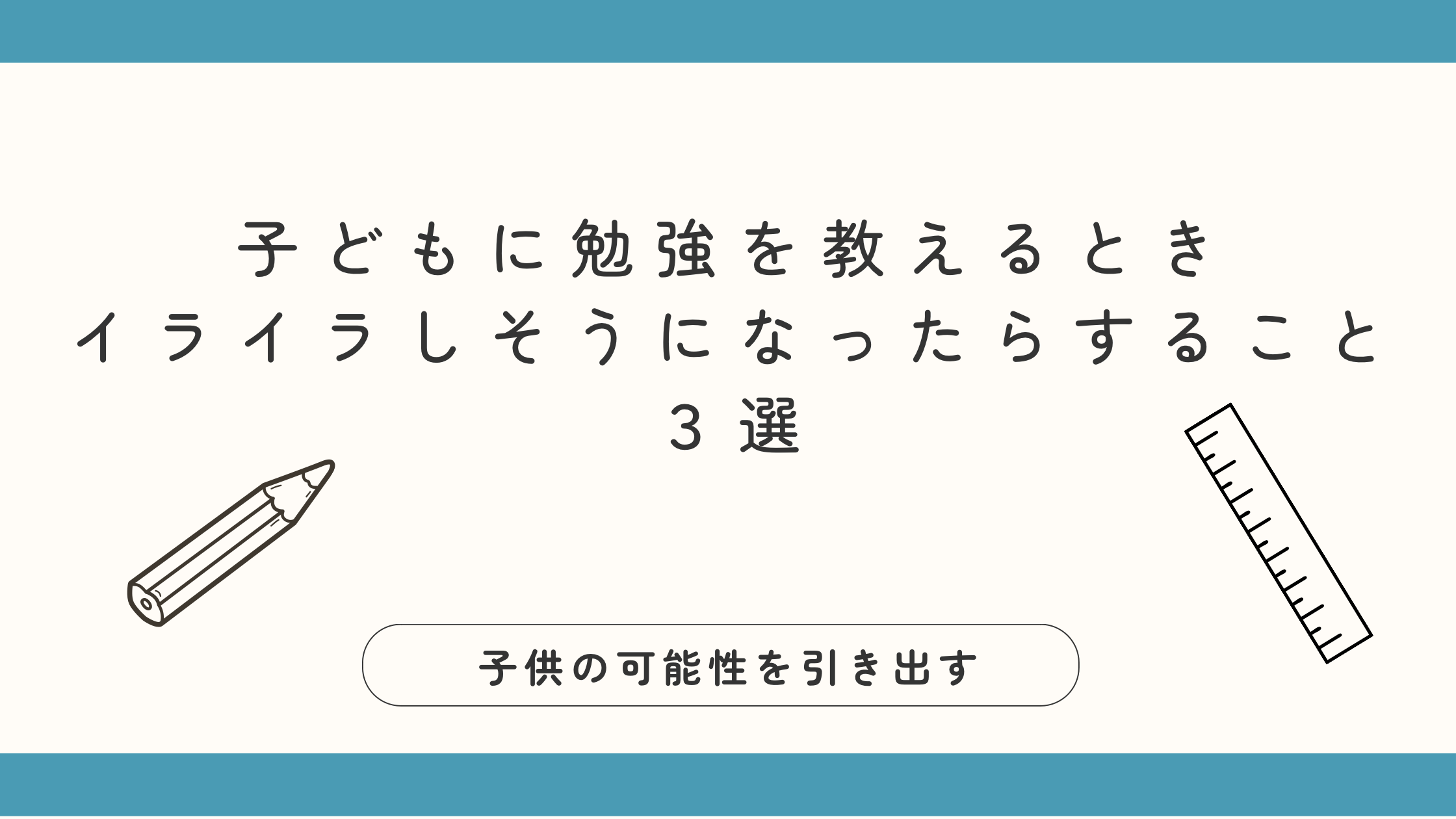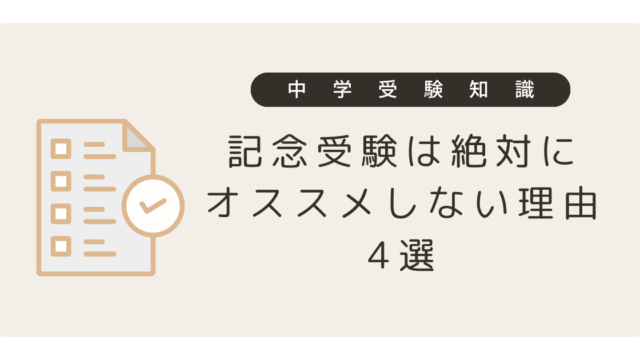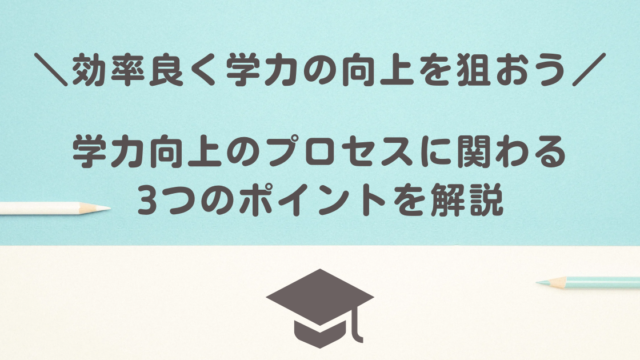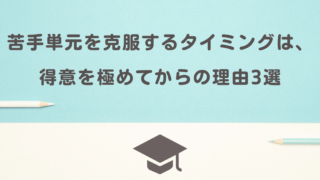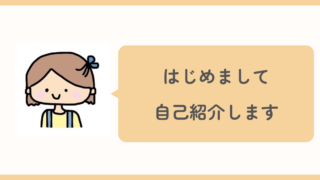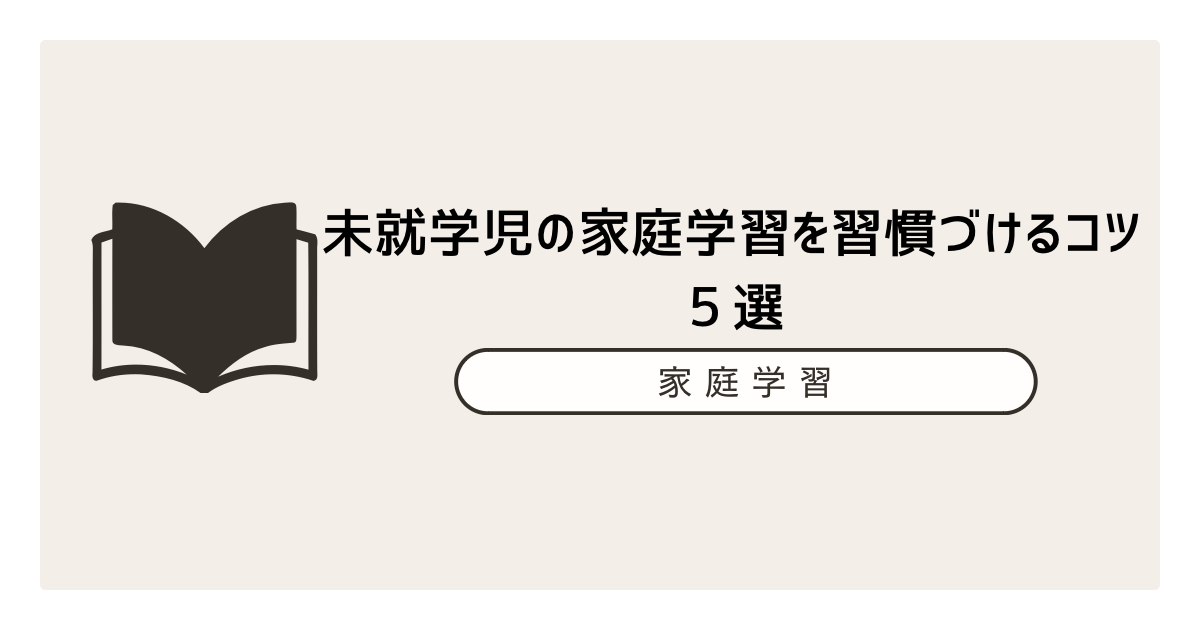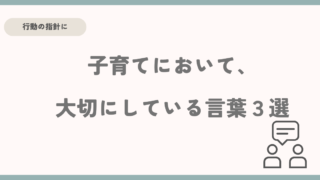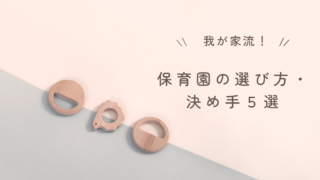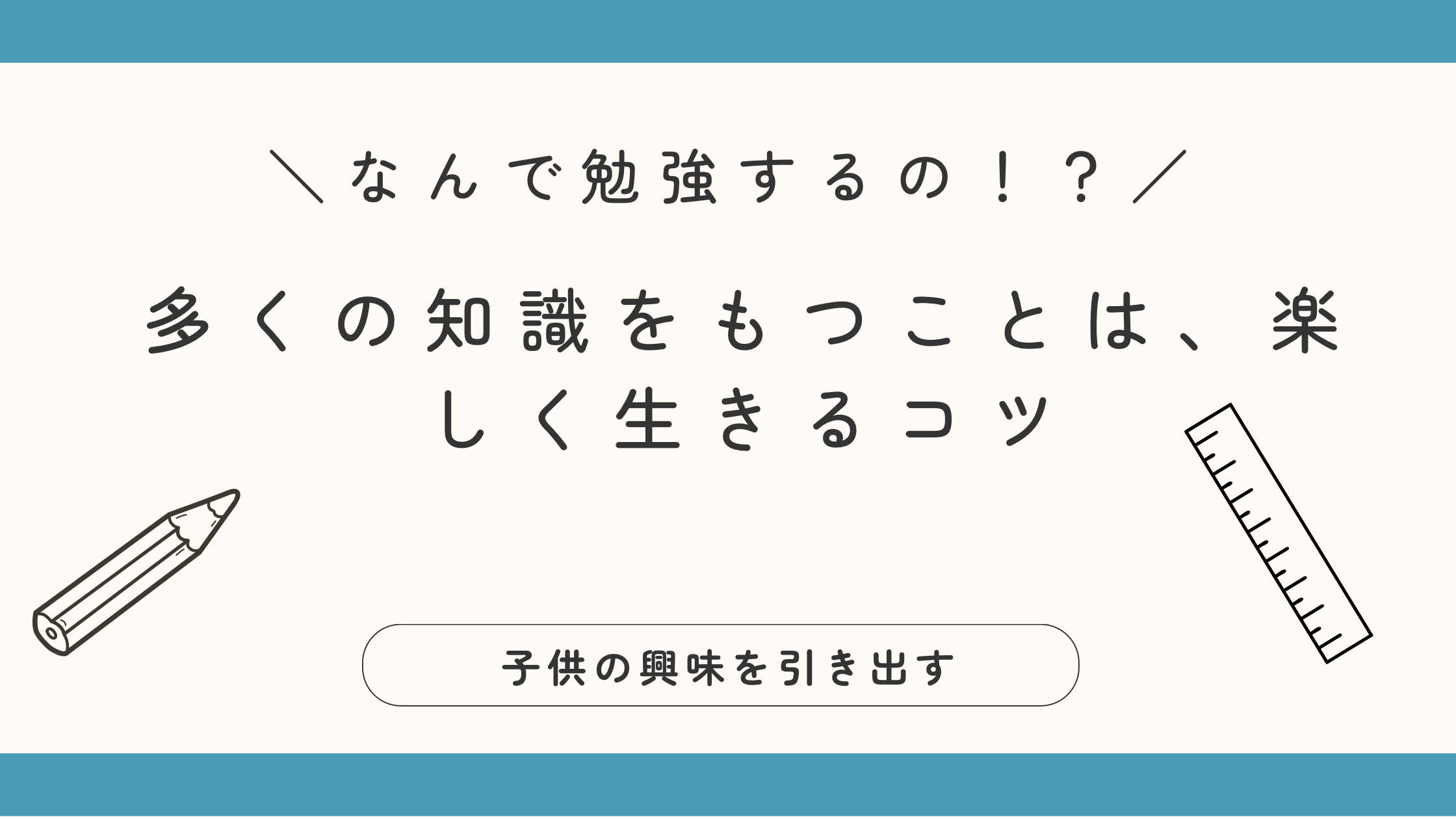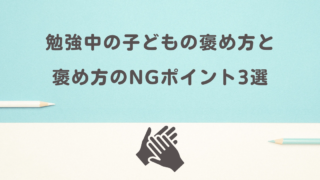子どもが勉強嫌いで、なかなか勉強に積極的にならずに困っています…。
前は学校の宿題も進んで取り組んでいたのに、今は全然で。
宿題をやらせるにも、一苦労です。。。
上記のような悩みを抱えている保護者の方、多いのではないでしょうか・
子どもが勉強に対して腰が重いと、こちらも嫌気がさしてしまいますよね。
・子どもが勉強嫌いになる理由の原因を探る。
・そうすることで、親御さんの対応も変わってくるかも!?
勉強っていつから嫌いになるんだろう!?
子どもが勉強を「嫌い」と認識し始めるのは、だいたい小学3年生頃だと言われています。
小学生の低学年の子に勉強は好きかを尋ねると
勉強好きだよ~!!
とポジティブな回答が多い印象です。
「めんどくさい」「宿題は嫌い」という回答であっても、
「めんどくさい。でもできないことはない。」
「宿題は嫌い。でも宿題ができないわけではない。」
というニュアンスが込められていることが多いです。
では、小学校3・4年生ぐらいから、どんどんネガティブな意見が出てきます。
学年が上がるにつれ、「勉強」に対してネガティブな感情を持ってしまうのは、なぜでしょうか。
勉強が嫌いになってしまう原因
勉強が嫌いになってしまう原因は、
ずばり!!「勉強が難しい」からです。
当たり前ですね。
大人の私たちも、勉強は難しくてとっつきにくいもの、と感じてしまいがちですが、一体いつからこのようなイメージがついてしまったのでしょうね。
「1+1」を難しいと感じた日はあったのでしょうか?多くの人は、初めから「1+1=2」と簡単に答えられていたのではないでしょうか。
一般的に、「小学3年生頃から勉強が難しくなる」と言われています。
人は基本的に「できることは好き」「できないことは嫌い」です。
勉強も同じで、できないから嫌いなのです。では、なぜできないかと言うと、難しいからです。なぜ、難しいかというと、それは「イメージが湧かない」からです。
「どういうこと!?」となった人、多いかと思います。解説していきます。
小学1・2年生と小学3年生の勉強の内容の違い
小学1年生の勉強内容
多くの小学生が最初に苦手な科目となるランキング1位は「算数」です。
算数って難しいですよね。
算数を例にとって話を進めていきます。例えば小学1年生の問題です。
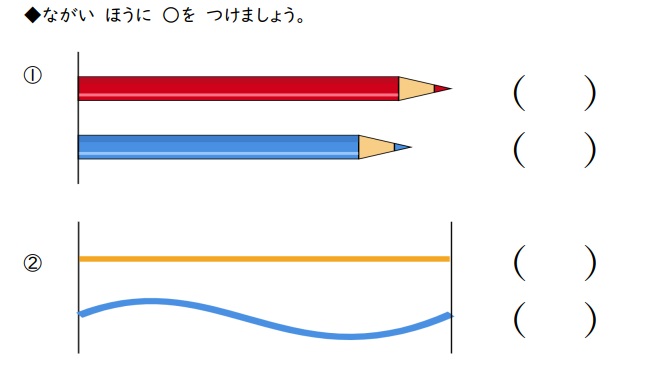
長さの単元の問題です。
どちらが長いか見ただけで分かりますよね。うちの5歳の未就学児でも分かりました。
「見るだけで分かる!」というのは大きなポイントです。
見るだけ分かれば覚えることは特にないですし、すぐに問題を解くことができて達成感に繋がります。
「この、鉛筆短くなったから書きにくいな。新しい長い鉛筆に変えよう」とか、
「髪長くなったから、短く切りたいな。切ったらサッパリして気持ちいいな」とか、
小学1・2年生の勉強って、日常生活と直結していることが多いです。
だからイメージがつきやすく、特に覚えることもないので、「簡単」となるわけです。
小学3年生の勉強内容
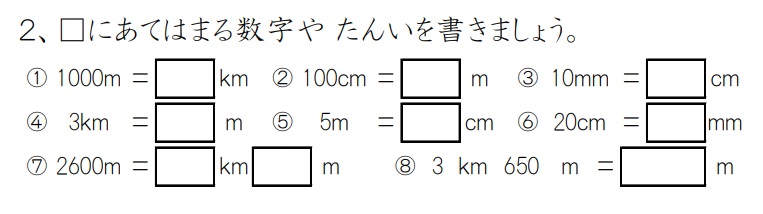
いきなりめちゃくちゃ難しい単位の変換の単元です。
2年前は、「どちらが長いでしょう??」と絵や図が入った問題を解いていたのに、
もう単位変換とは、子どもの成長は早いということなのでしょうか!?
この問題の一番難しいところは、「1kmの距離ってどれぐらいか分かる?」というところです。
私の小学3年生の甥っ子に、「1cmってどれぐらい?」と聞くと、「これぐらい」と指で長さを作ってくれました。
「1mってどれぐらい?」と聞くと、身長から推察して、「ここぐらい?」と自分の首の高さぐらいを指してくれました。
「家から1km離れた場所ってどこ?」と聞くと、「うーん…」と黙ってしまいました。
「イメージが湧かない」とはこういうことです。
1kmの長さが具体的にイメージつかないのに、3km650mは何m?と聞かれてもよく分からん!となりますよね。
「1km=1000m」と頑張って覚えても、そもそも1kmがよく分かってなかったら、
イメージがつかず、イメージがつかないものってすぐ忘れていってしまいます。
学年に上がれば上がるほど、勉強内容が、日常生活では経験しないことが多くなっていくため、難しくなったと感じるのです。
個数でも、小学3年生になると「大きな数」という単元で1億や1兆という単位が出てきます。
100枚の折り紙は実際に見たことがあり、「100」という数字はイメージできても、
1億枚の折り紙は、なかなか見る機会ないですよね。
1億って言われても想像できず、想像できないものを考えることは苦痛であるため、
勉強に意識が向きにくくなるというわけです。
「分かる=できる」ではなくなっても、頭が悪いというわけではありません。
「小3から勉強が難しくなるから、塾に入りましょう!通信教材をしましょう!」等、営業目的で言われることはありますが、
親も子どもも、上記の原因をあまり知らず、小学1年生のときと同じ勉強時間、量をこなします。
宿題が分からなくて解けない。
学校の授業では分かっていたはずだったのに。もう1回教科書読み直すこと面倒くさいな、勉強嫌だな、したくないな。
と思うわけです。小学1・2年生までは「分かった=できる」だったのに、小学3年生になると、宿題やろうとしても、解けない問題が増え、
「私(僕)って頭悪いだ!」と思い込んでしまうわけです。親も、我が子の勉強の様子の変化やテストの点数を見て、
小学校2年生までは、テストも100点が多かったのに…。3年生になってから、すごく下がってしまったわね。
やっぱりうちの子頭悪いんだわ。遺伝だもの、しょうがいないわ。
と思ってしまうのです。
上記で説明したように、勉強内容のイメージが湧かないため、具体的なことに落とし込むことができず、手こずっているだけで「頭が悪い」というわけではないのです。
適切な勉強量と質をすれば、またテストの点数は復活しますので、ご安心下さい。
まとめ
以上が勉強が難しいと感じる理由でした。いかに、事象を想像できるようになるか、また、想像できるようになるための訓練が必要、ということですね。
幼少期に多くの経験をすべし!等、言われるのは、そのためでしょうか!?