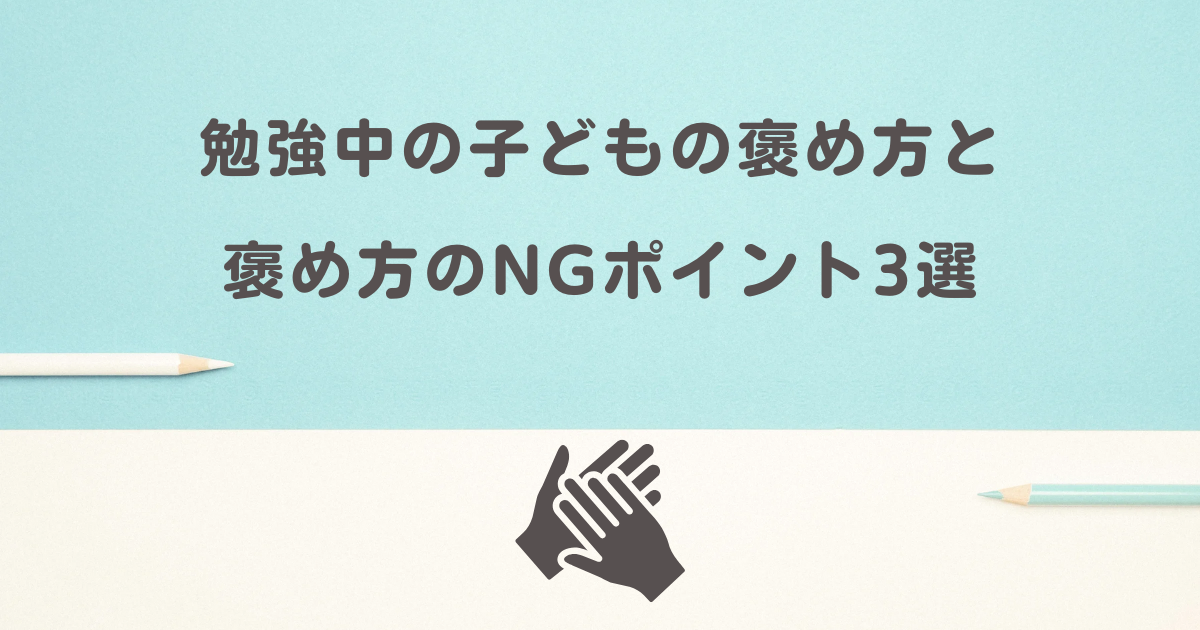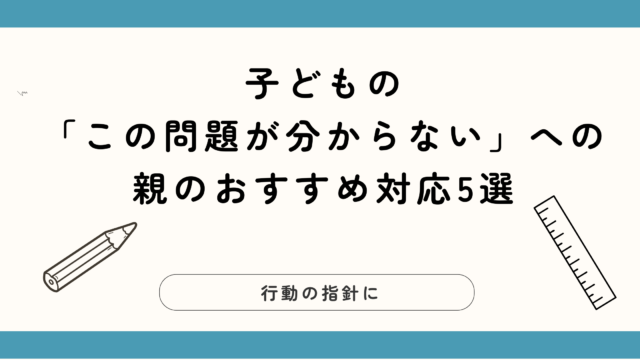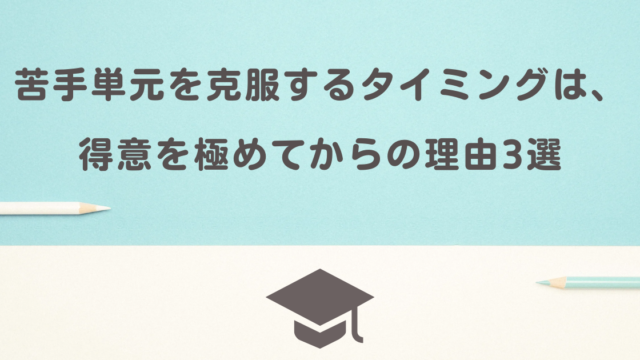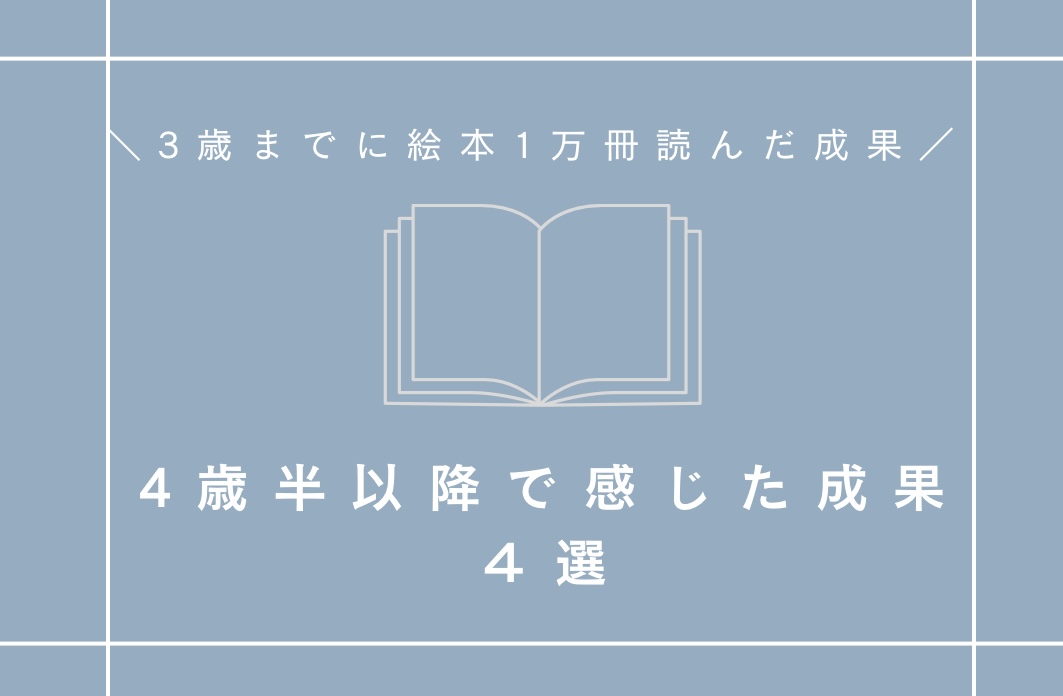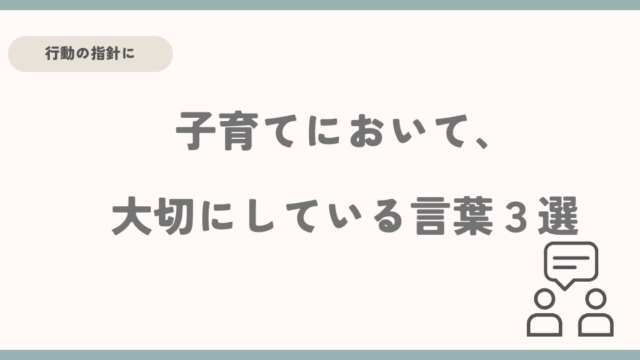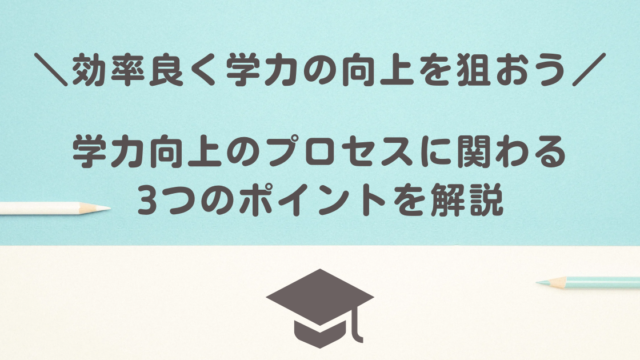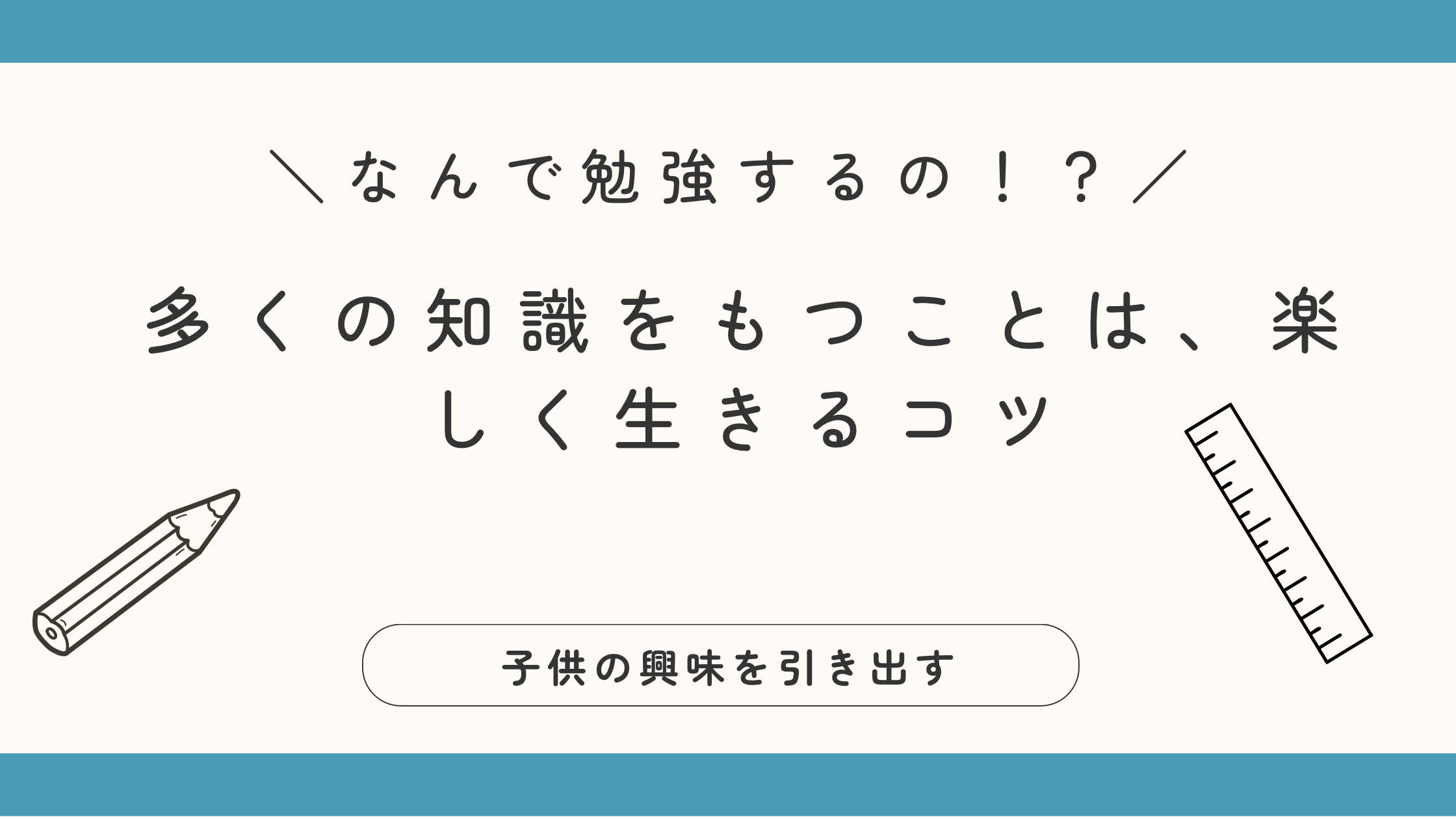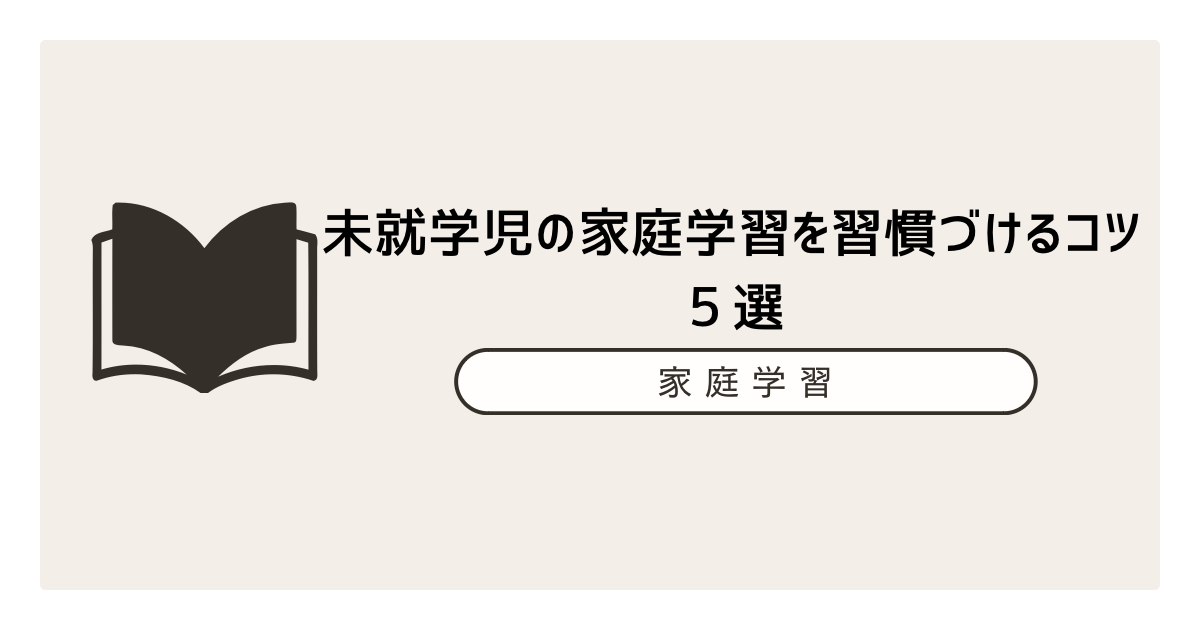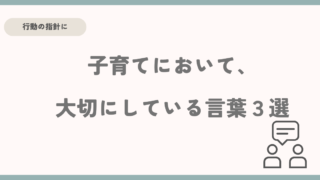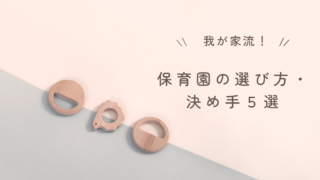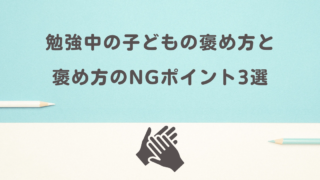子どもを褒めることの効果
「子どもを褒めましょう!」とよく言いますよね。
「褒められて育つと自己肯定感が高まります」とか、「何事にも挑戦できるようになります」とか、少し調べると褒めることのメリットがたくさん出てきます。
親としては、子どもが勉強しているときに褒めて、子どものやる気を上げたい!と思いますよね。
でも実際褒めようとしても、悪いところばかり目について、何を、どのように、褒めたらいいんだろうと、考え込んでしますことが多いと思います。
具体的な褒め方やシーンを解説していきます。
子どもの褒め方
褒め方が分からない場合や、わざとらしくなってしまいそうなときは「褒めよう!」と意識し過ぎず、「伝える」という意識を持ってみるといいかもしれないです。
親が「良い」と思ったことを、事実として伝える。
「なんか褒めなきゃ、なんか褒めなきゃ」と思うと、何も出てこなくなりますし、
「褒めてあげよう」「褒めて、勉強へのモチベーションをあげて、もっと勉強してほしい。」という下心で褒められても、子どもは案外嬉しくないものです。
親が、本当に良いと思ったことを、思った通り口に出してあげればいいのです。
例えば、「計算問題、解くの早くなったなぁ~」と思ったら、
そのまま「計算問題、解くの早くなったね。」と言えばいいのです。
事実を伝えているだけですが、子どもにも「問題を解くスピードが早い=いいこと」という認識があるため、褒められていると感じる子が多いでしょう。
当たり前にしていることを、改めて伝えてみる。
「いいと思うところなんて見つけられないよ~」と思った人もいるかもしれません。
そんなときは、今、子どもが当たり前にできていることを伝えてみるのも一つの手です。
- 姿勢良く座っている。
- 真っすぐ線が書けている。
- 大きく濃い字で書けている。
- 消しゴムでの消し方がキレイ。
などなど。
案外、子どもができていることは多いものです。
「姿勢、すごいいいね~」「大きい字で書けてるね」「消しゴムでキレイに消せたね」等、
親がニコニコな顔で言うだけで、子どもは嬉しいと思います。
半年前の子どもの写真や動画を見て、半年前にはできていなかったけど、
今は当たり前にできるようになったことを探してみるのもいいかもしれませんね。
過去と比べて、変化・できるようになったことを伝える
以前は出来なかったけど、できるようになったことを伝えるということも一つの手法です。
大した変化ではなくても、少しの変化でも大丈夫です。
例えば、
「前は枠からはみ出して書いちゃってたけど、今日は、枠ピッタリにはまってる~~」とか「前はこの問題、間違えてたけど、今日は正解してる~」とか、
子どもの成長や変化を一緒に喜ぶことも、褒めるということなのです。
子どもを褒めるときの超重要ポイント
上記3点のように褒めよう(伝えよう)と思ったときに、
しなければならないことは「普段の子どもの様子をよく観察すること」です。
言ってしまえば、褒める内容はなんでも良くて子ども自身も褒められた内容よりも、
「お母さんが褒めてくれた」「お父さんが私のこと見守ってくれている」「お母さんが私を認めてくれている」と、
大好きなお母さん・お父さんが自分のことに関心を持ってくれている=大切にしてもらっていると感じ、自己肯定感が上がります。
「テスト結果だけを褒めるのでなく、テスト結果を得るまでの頑張りや工夫の過程を褒めましょう」とよく言われます。
今日は、どんな様子で勉強に取り組んでいるのかな、問題の出来具合はどうだろう、と子どもの様子に興味を持ち、現状や変化を伝える、ということが、過程を褒めるということなのではないでしょうか。
こんな褒め方は注意!
個人的には、褒めること自体にデメリットはあまりないのではないかと思っていますが、注意すべき褒め方はあると思っています。
子どもの行動と異なることを言って、大げさの褒める。
例えば、子どもに字を丁寧に書いてほしいと思い、本当はそこまで丁寧に書けていないと思っていても、
「字、丁寧に書いてるね~。」など言ってしまうと、子どもはこれでいいんだ、と思い大人の裏の意図を見てはくれません。
このように褒めていると、親と子の解釈の差がどんどん開いていくため、オススメできません。
他人と比較して褒める。「〇〇ちゃんよりも~」
「〇〇ちゃんよりも上手だね」等、誰かと比較しながら褒めることは、事実を伝えているとしても良くありません。
自分よりできない人を探して、「この人より出来ているから自分は偉い!」と、安心を求めるようになります。誰かと比較し始めるとキリがありません。
上には上がいますからね。
「数学のテスト、クラスで1番だった!」と思っても、学校順位は5番で、誰かに負けてしまった、といつまでたっても満足感が得れなくなってしまいます。
「自分は自分!」と自信を持って何事にも取り組めるような子に育ってほしいと思いますが、
常に誰かと比較して落ち込んだり喜んだりする子になってしまう可能性もあります。
親の都合で褒め方や基準が変わる。
親の気分次第で、褒められる基準や叱られる基準が変わることのは、本来あまりいいことではありません。
しかし、親も人間なので、仕方のないときもあると思いますし、少しぐらい子どもに理不尽なことがあっても、それも子どもにとっての一つの経験だと考えています。
ただ、極端に変わりすぎることは良くないです。
今日は、褒められていたのに、次の日は叱る!といった両極端な対応は気を付けた方がいいです。
また、褒める際も、親の機嫌が良いからと言って、約束もしていないお菓子やおもちゃのご褒美を買うなども避けた方がいいです。
子どもが混乱してしまい、行動の善悪を身に着けにくいためです。
(もちろん、事前に「ピアノの発表会頑張ったら、〇〇買ってあげるね」と事前に約束していたら、ご褒美作戦は、個人的にはありだと思っています。)
まとめ
以上が、子どもの褒め方のポイントでした!私はいつも「伝える」を意識して、子どもとコミュニケーションを取るように心がけています。
ちゃんと褒めなきゃ、とプレッシャーに感じなくても大丈夫です。
子どもの素敵なところを見つけ、自然に伝えられるようになるといいですね。
参考になれば嬉しいです!