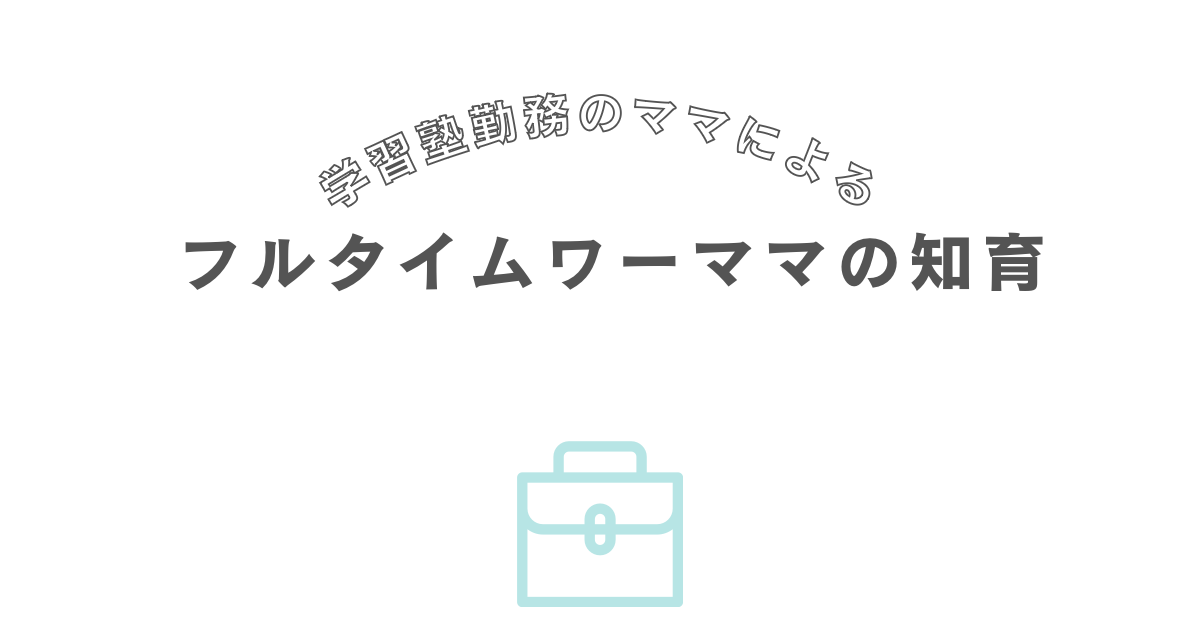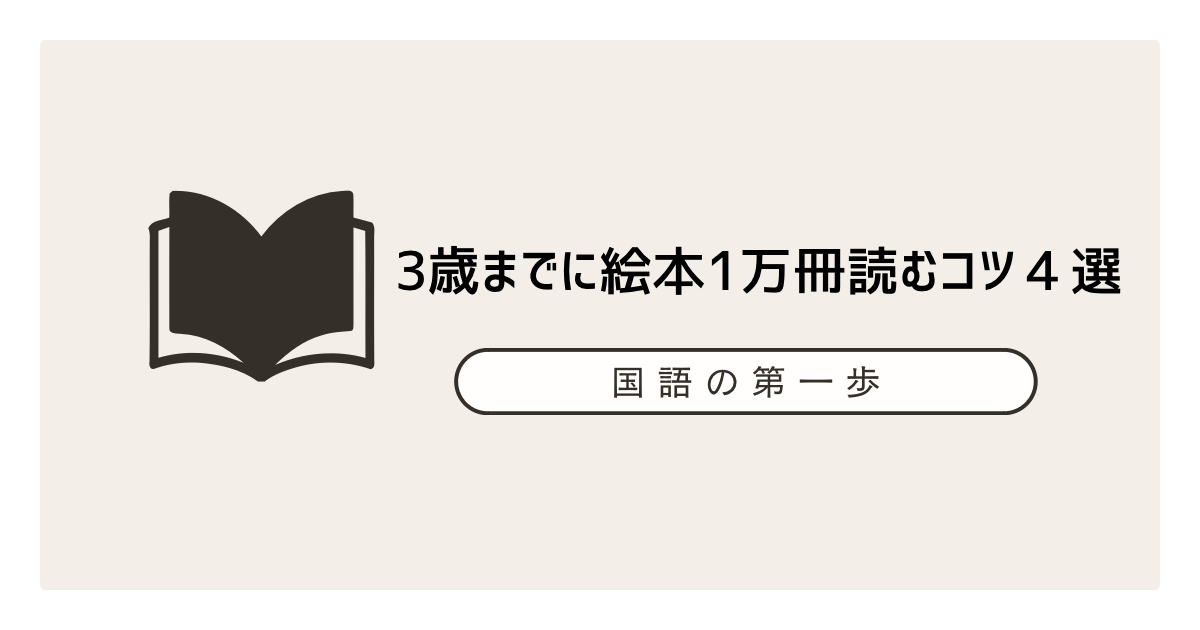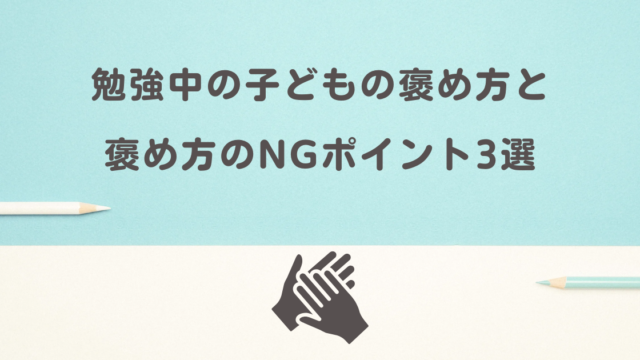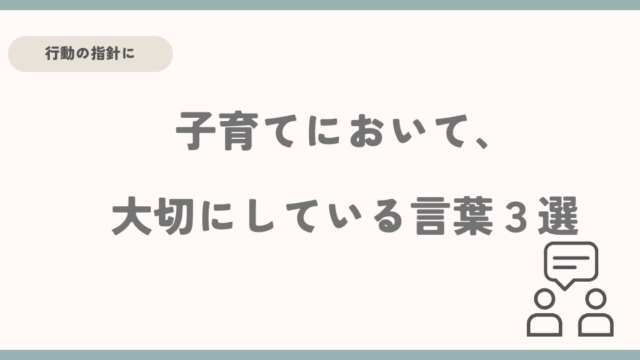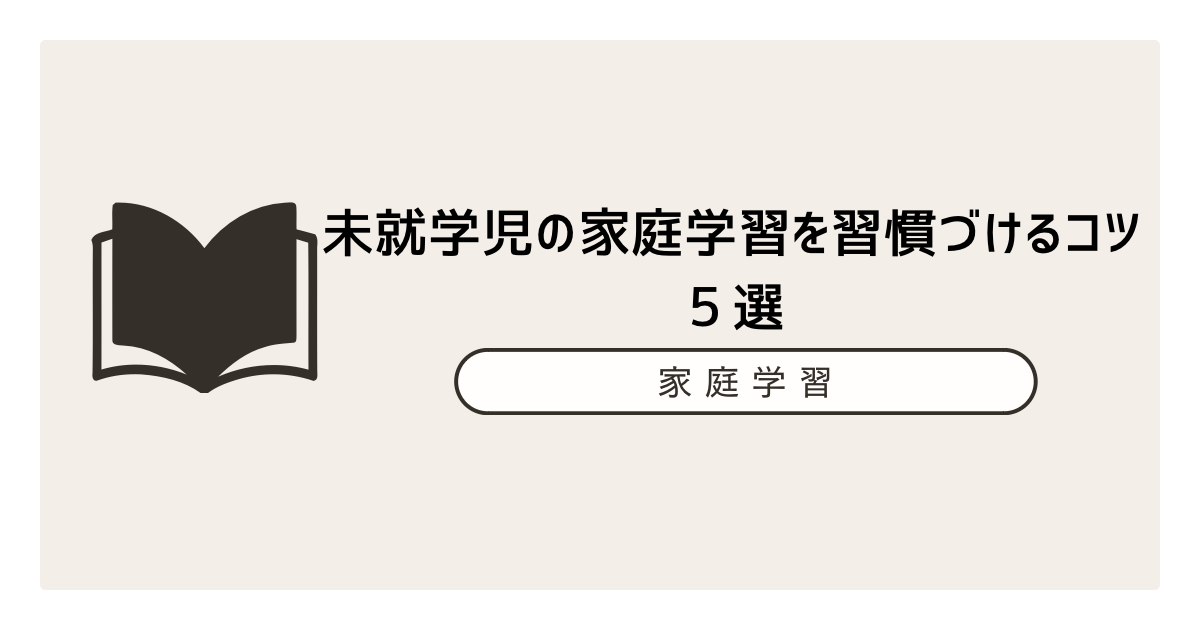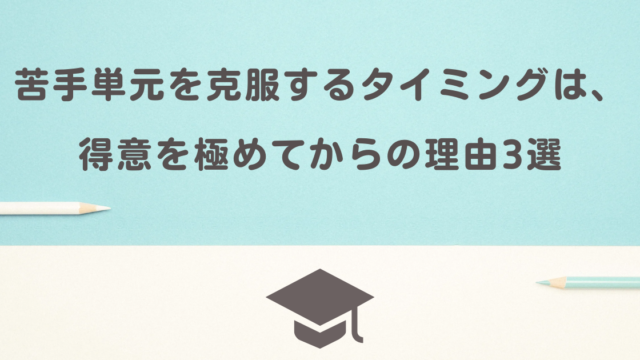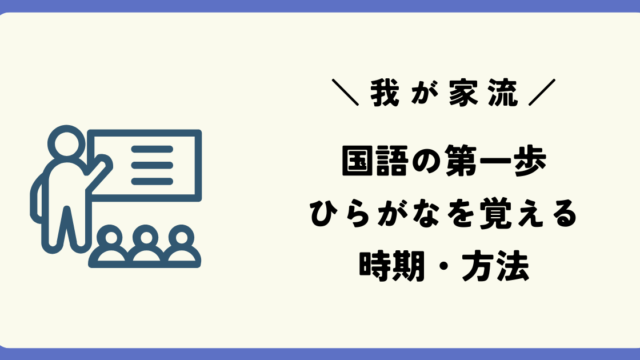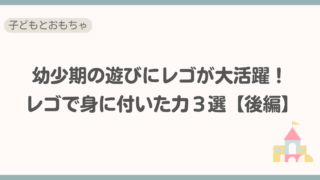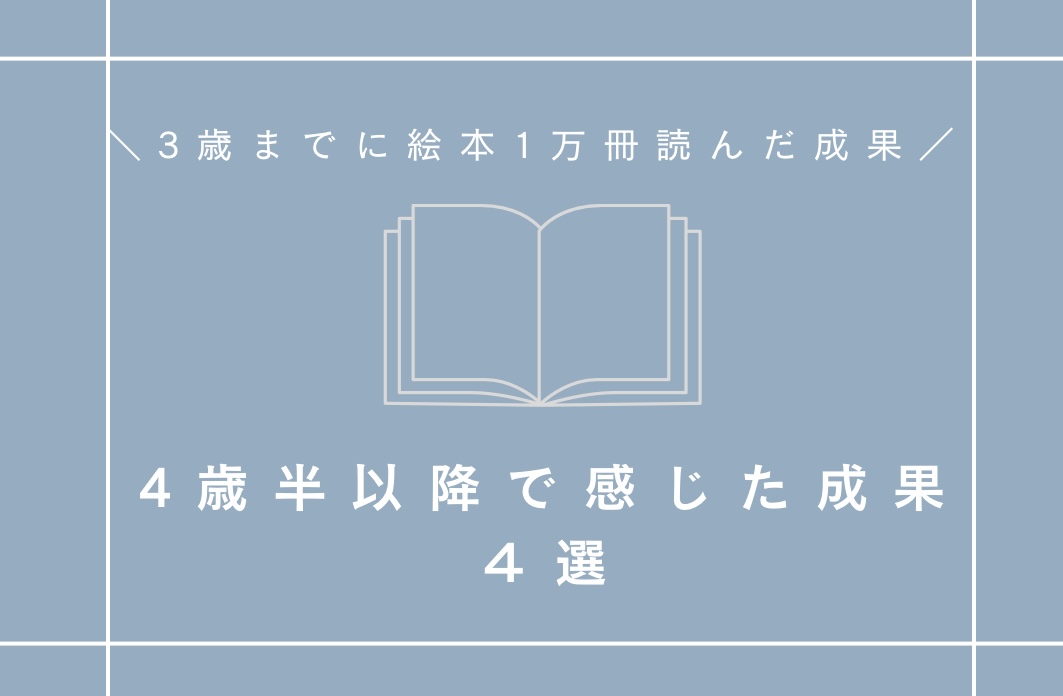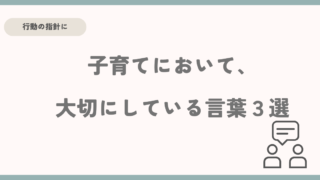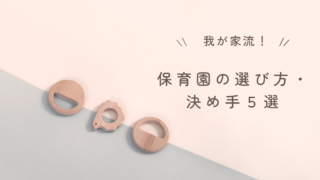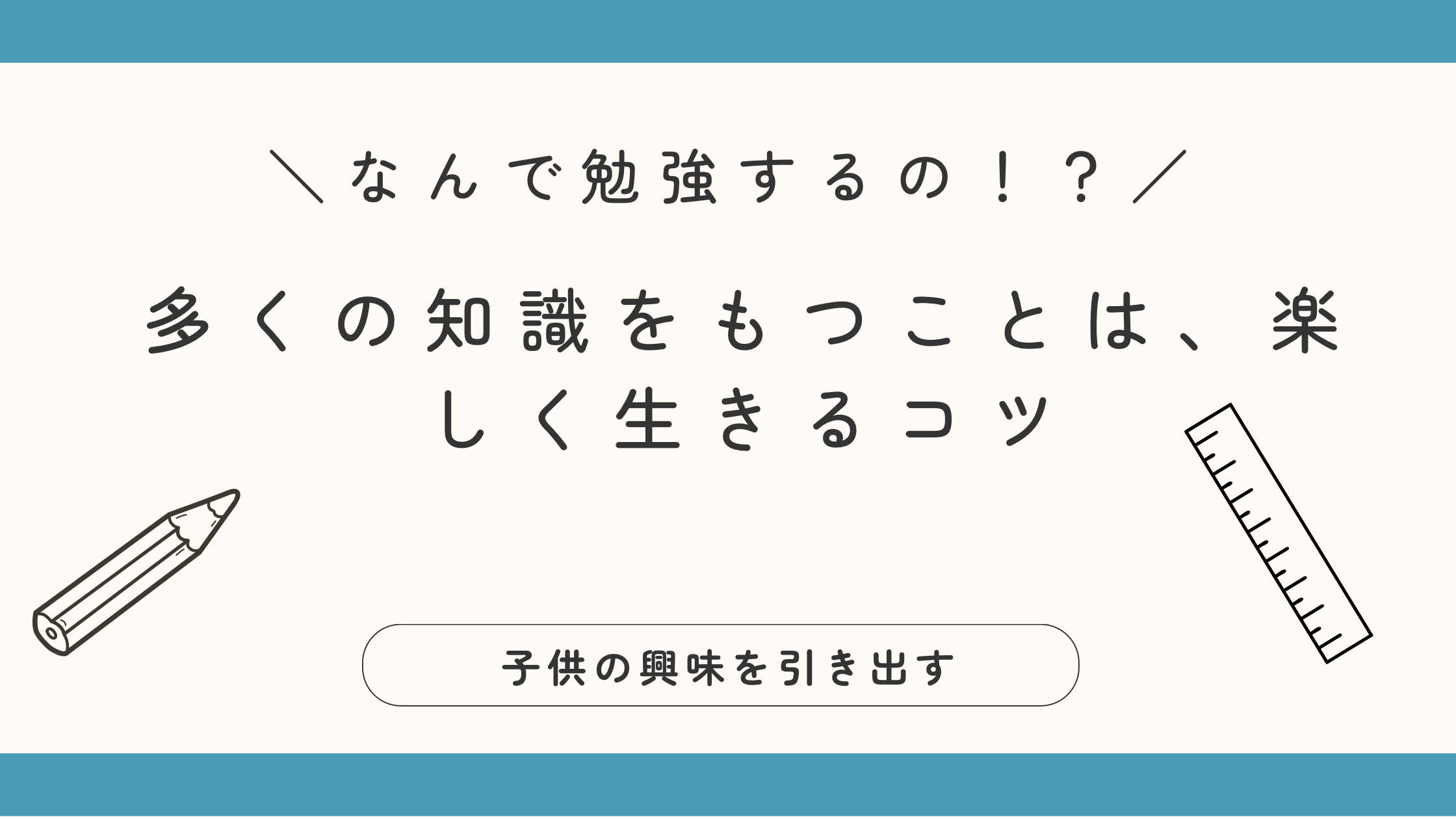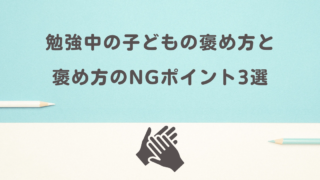夫婦ともにフルタイムの正社員です。平日は時間の余裕がなく、夕方子どもを保育園に迎えに行って、ご飯・子どもの世話・お風呂・明日の準備・寝かしつけ等々していたら、あっという間に20時・21時で寝る時間です。知育や家庭学習をする暇がありません。こんな感じでいいのでしょうか?
分かりますっ!!時間って本当にないですよね。
最近は、フルタイムで働くママは多いのではないでしょうか!?
私もフルタイムで働く正社員です。
フルタイムでなくても、働くママは多いと思います。
「2021年国民生活基礎調査の概況」によると、児童のいる世帯において、母親が仕事をしている世帯の割合は75.9%だそうです。
私もそうですが、働くママはとにかく時間がないっ!!!
SNSや育児本で書かれている、子どもの発達に良さそうな働きかけの知育や幼児教育、たくさんあります。
全部やらなくちゃ!全部やらないと、子どもは賢くならない!!と、
ついつい思って焦ってしまいます。
焦っても、時間が作れるわけではないため、自分自身のマインドセットをしていく必要があります。
本日は私がしている、ワーママとしての心得を紹介したいと思います。
フルタイム正社員のワーママのマインドセット
しないことを決めて、しないことは絶対にしない
知育・幼児教育のやり方や種類は多種多様です。
特にSNSで、「こんなことすると、発達にこんないい影響がありますよ〜」みたいな投稿があると、できない自分に嫌気がさしてしまいます。
子育てにおいて、睡眠と気持ちの余裕は非常に重要です。
親がキリキリした精神状態で子どもに接することは、子どもの心の成長にとっても良くありません。
親の顔色を伺って生活することが、日常になってしまいます。
子どもの前向きなチャレンジや健全な心は、愛情が土台になっているからです。
私は、「しないことはしない!そういう投稿を目にしても、焦らない、落ち込まない!」と決めています。
我が家の場合、以下のことは、取り組みたい項目ではあるものの、時間的にも気持ちの余裕的にも無理だと思い、スパッと諦めました。
・1歳でも片付けしやすいようなおもちゃの配置や、物を取り出しやすい配
置にすること。
・カード系の知育・幼児教育
・自立を促すような声かけ、働きかけ
1歳でもお片付けしやすいようなおもちゃの配置や、物を取り出しやすい配置にすること。
0歳からの赤ちゃんでも、おもちゃを取り出しやすいように、
遊ぶおもちゃを赤ちゃんが選び取ったり、お片付けを促せるような、おもちゃを見せる棚というものがあり、SNSの発信でよく目にします。
非常に魅力的ですが、我が家では諦めました。時間を優先することにしました。
子どものおもちゃや絵本は、親が片付けしやすかったり使いやすい配置にしています。
親が取り出さないと、取りにくいおもちゃたくさんあります。
片付けも、1・2歳が一人でお片付けをできる配置にはなってないです。
寝る前に、親がポイポイ、箱に入れて完了!みたいな感じになっています。
寝る時間(20時就寝)を優先していますので、その日の時間によって子どもと一緒にお片付けをするときもあれば、
親が急いで「お母さん、片付けちゃうねーー」と、自分で片づけちゃいます。
1・2歳のときは、片付けを促す働きかけは、あまりできていませんでしたが、
5歳になった長男は問題なくお片付けできているので、まぁ良しとしています。
↑このような箱付きのおもちゃはありがたいです。
こういうレンタルもいいですよね(^o^)
カード系の知育・幼児教育
フラッシュカードや数字カードなどのカードを使った知育や幼児教育です。
最初、SNSの数ある投稿に触発され、私が育休中に、我が家でも導入してみました。
しかし、コストがかかりすぎてしまうのと、私が楽しめきれなかったことと、絵本に全振りすることを理由に諦めました。
休日にするだけでもいいのかな~とも思いましたが、
(私が)楽しめない物をノルマとして課すことに、さらに楽しくなくなると思い、きっぱり諦めました。
休みの日は、親も子どもも、ゆっくりのんびり過ごすことを一番に優先しました。
自立を促すような声かけ、働きかけ
よくSNS等で、子どもが自分のことは自分でできる動線を、といった感じで、身の回りのことを自分でできるようにする方法がよく掲載されています。
子どもが小さいうちから、自分でお着替えできるように、保育園や幼稚園から帰ってきたらカバンは所定の場所において、など、ほんとに些細なことですね。
早いうちから、自分のことは自分でしてくれたら、非常にありがたいのですし、大切なことだとは重々承知ですが、
我が家は、きっぱり諦めて親が一番楽な動線を作っています。
一応「洗濯物出してよー!」「自分でリュック持って」など、それっぽいことは言い、
やってくれたらラッキー程度にしといています。
親が先回りしてやることは、よくないと思うので、しないように気をつけていますが、
子どもにお願いされたら、比較的すぐに手伝うスタンスをとっています。
5歳になった長男は今でも、家ではまだまだ甘えん坊ですが、
人前や保育園では自分のことは自分でできているっぽいので、良しとしています。
「絶対に毎日継続すること」を決める
しないことを決めたら、次は絶対に毎日継続することを決めます。
決めたことは、私がどんなに忙しくても疲れていてもすると決めています。(※体調不良や、どうしてものイレギュラー時は除く。)
我が家で決めたことは、以下の通りです。
・絵本の読み聞かせ(3歳までは1日10冊~15冊)
・家庭学習のプリンやワーク
・毎日の食事は手作りで
絵本の読み聞かせ
絵本の読み聞かせは、最重要優先事項にしていました。
特に、長男が絵本大好きマンということもあり、無理なく毎日継続できました。
関連の記事も参考にしてください。
家庭学習のプリントやワーク
3、4歳から始めて、今は、1日15分〜20分程度の家庭学習です。
我が家は七田式のプリント3枚と、ひらがな・カタカナ練習帳したり、脳トレ的なワークをしたり、しています。
小学生になる前に、家庭学習の習慣はつけておきたいです。
家庭学習は、学年が上がれば上がるほど、0を1にするのが難しいのです。
0分の勉強時間を10分に習慣化するのが大変です。
ただ10分でも学習時間があれば、それを30分、1時間にすることは、そこまで困難ではありません。
そのため幼児期から10分でも15分でも学習習慣をつけておきたいのです。
毎日の食事は手作りで
昼食は保育園で食べてくるため、朝食・夕食を自宅で食べます。
献立は、お惣菜や冷凍食品は使わず、手作りとしています。
お惣菜や冷凍食品を一度使ってしまうと、何度も使いそうになる気がするのでなるべく使わない方向で考えています。
旬な野菜や果物の美味しさを感じることの経験はしてほしいです。
東大合格者を多く輩出する開成高校の生徒70%以上の生徒のお弁当はお惣菜や冷食を使わず、手作りなんだそうです。
私はあまり料理は得意ではないですが、子どもにつくる料理は料理本やクックパッド等を使って、頑張って作っています
「しないこと」「すること」以外のことは?
「しないこと」「すること」を決めたら、忠実に実行していくのみ。
その他のことは、できることだけ、できるときだけするようにしています。
例えば、ハサミやのりを使った工作、お絵描き、台所育児等、したいことはたくさんあります。
上記の「しないこと」「すること」以外のことは、できるときにやりたいことをする、としています。
休みの日に、子どもがしたいと言ったことで、親が気乗りしたこと(気乗りするように頑張りますが、どうしても疲れている時は別日に約束しています。)
逆に、親が提案して、子どもがしたいと言ったことを、しています。
ノルマとしないように、休みの日は親も子どもも、心穏やかに、やりたいことをする楽しい休息の日と捉えています。
まとめ
以上が、我が家の仕事と子育ての両立の心得でした。
「しないこと」を決めることが、勇気がいります。本当はやった方がいいことばかりですからね。
しかし、親の私はもちろん、子どもの時間も有限です。家族みんなが楽しく、心穏やかに過ごせることを最優先に、これからも考えていきたいと思っています。
我が家の一例が、参考になれば嬉しいです。