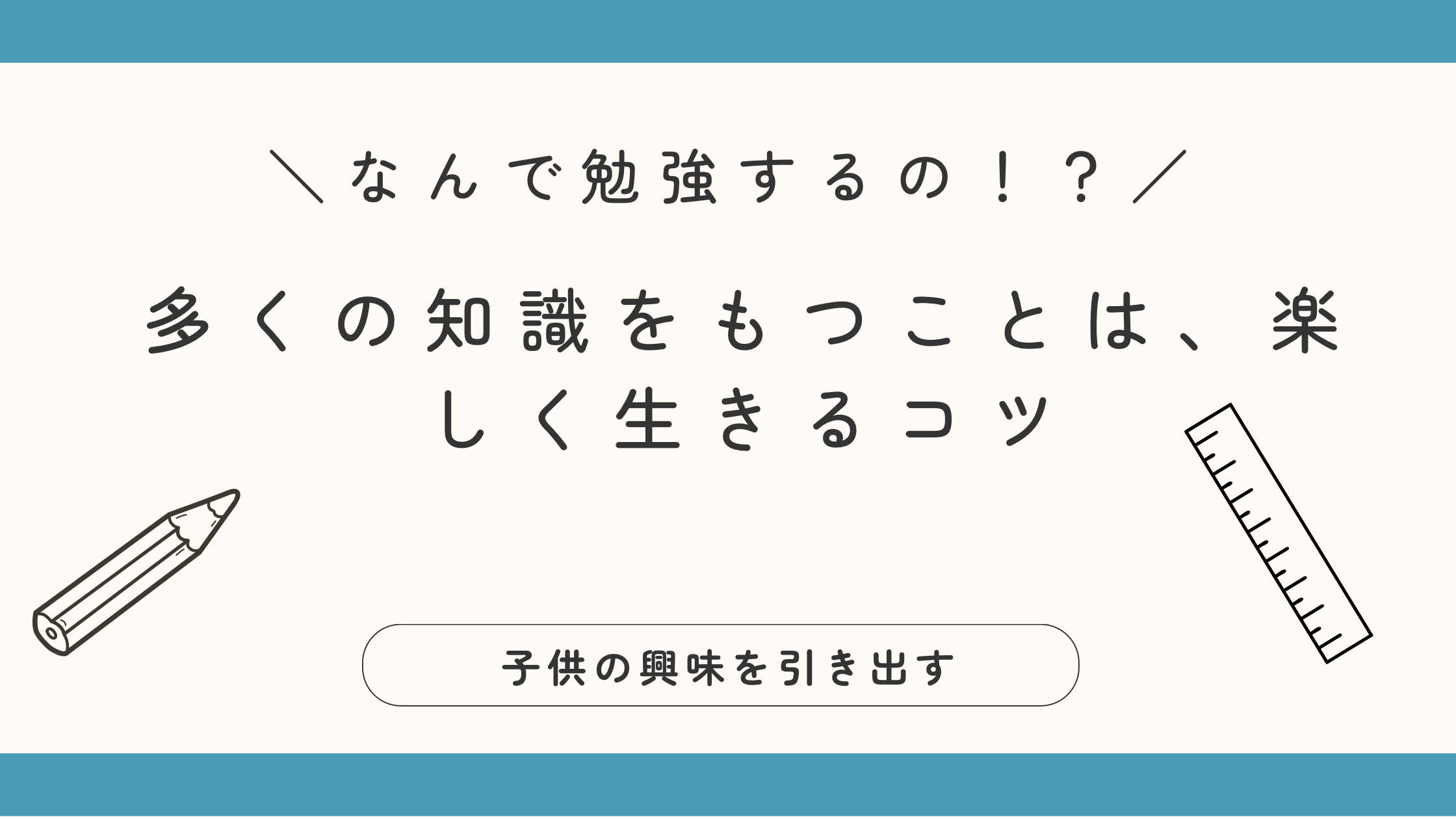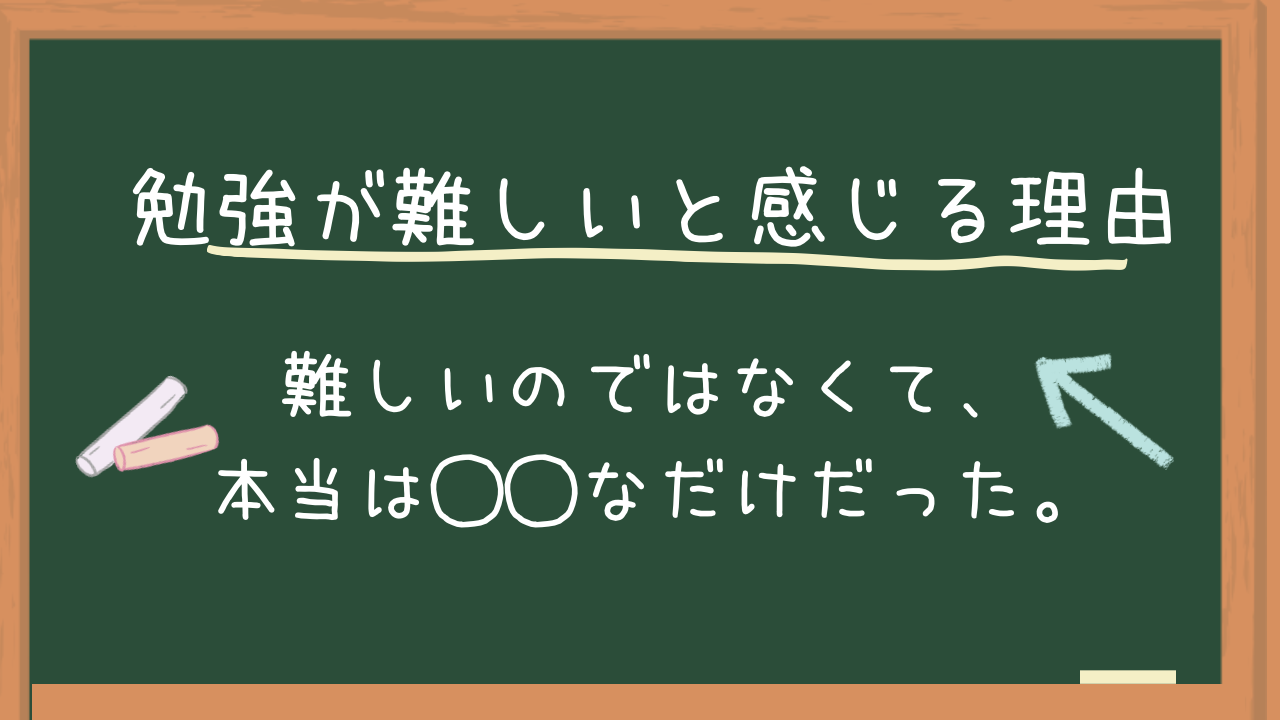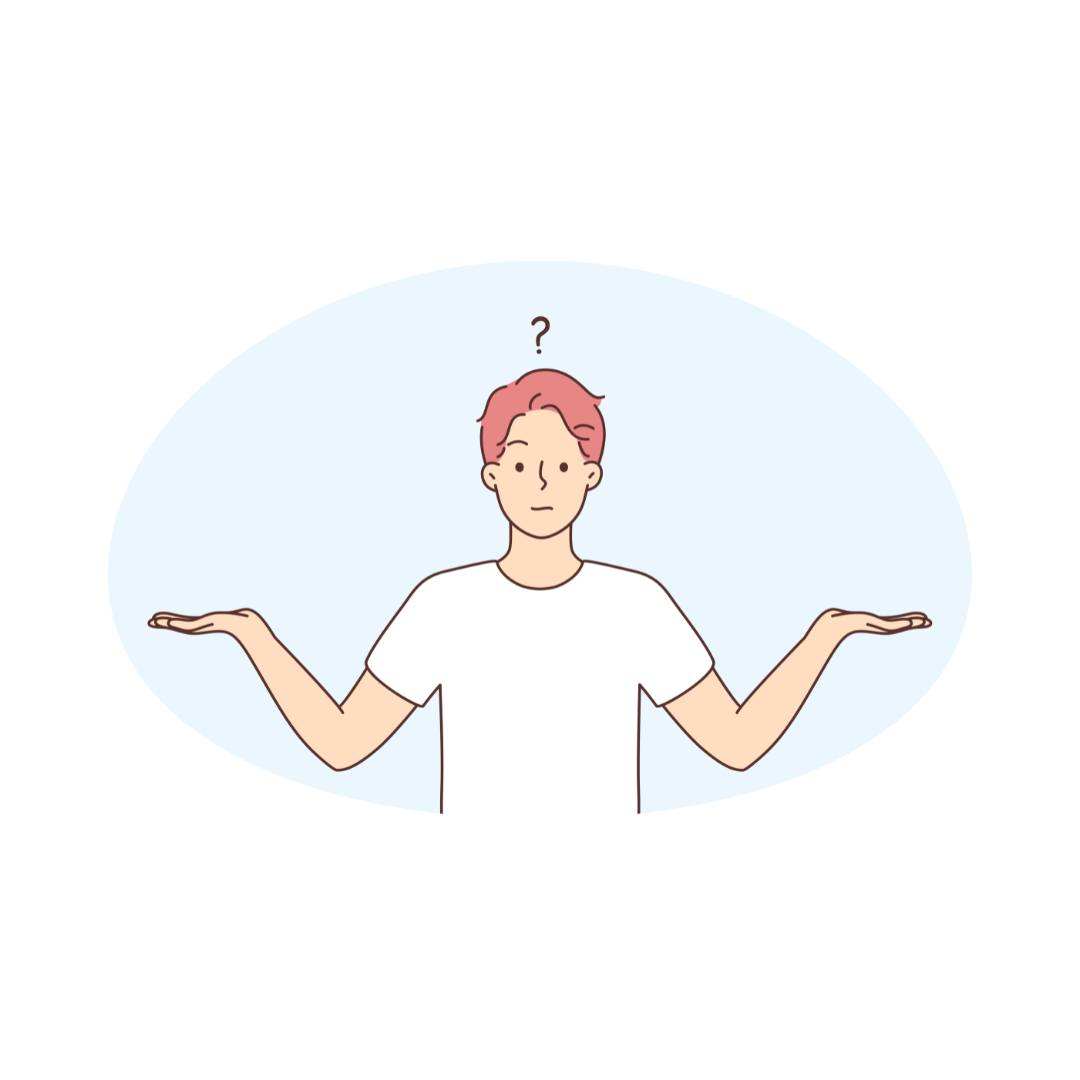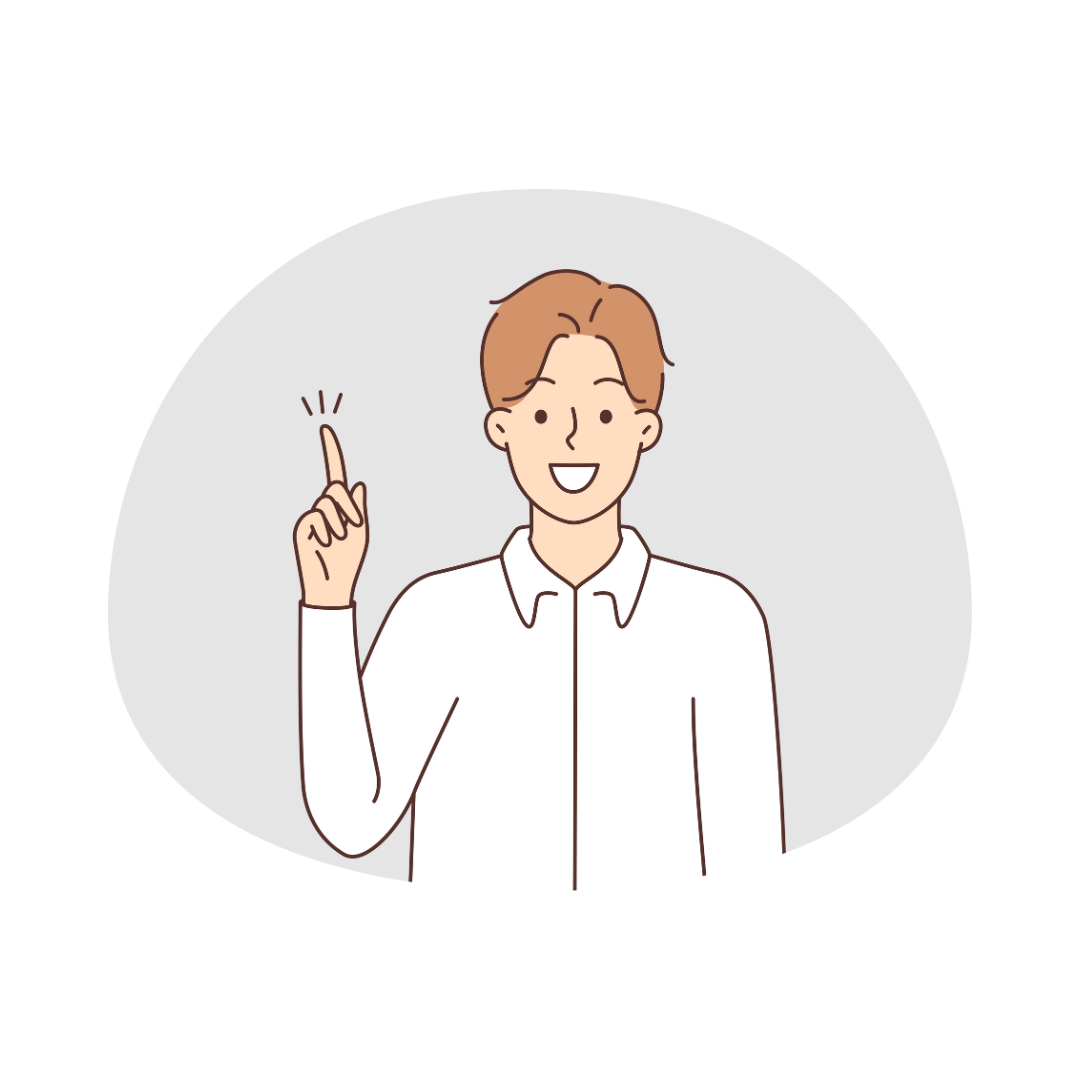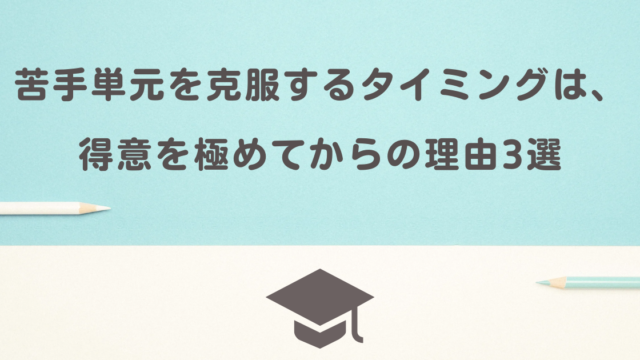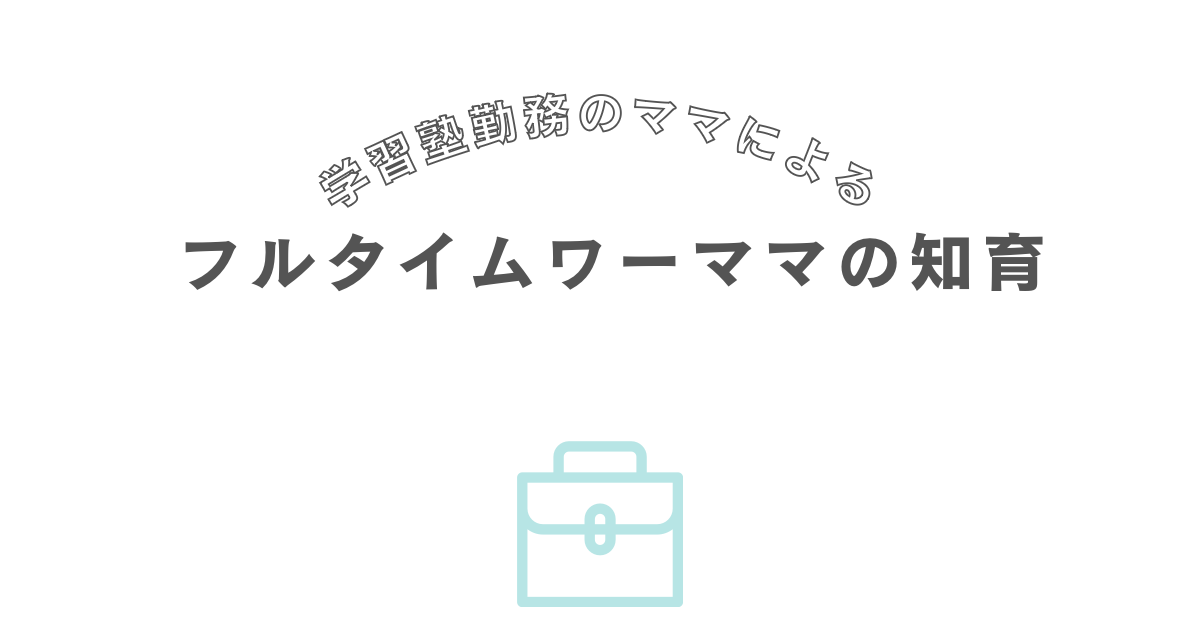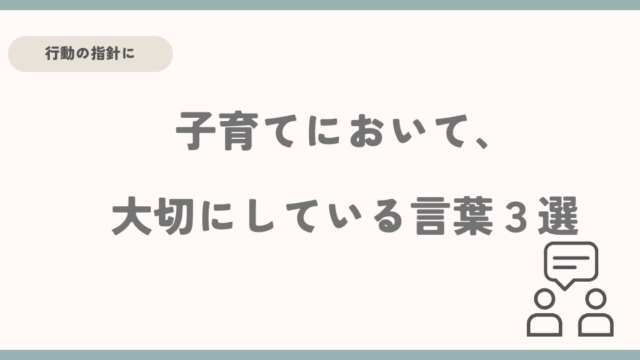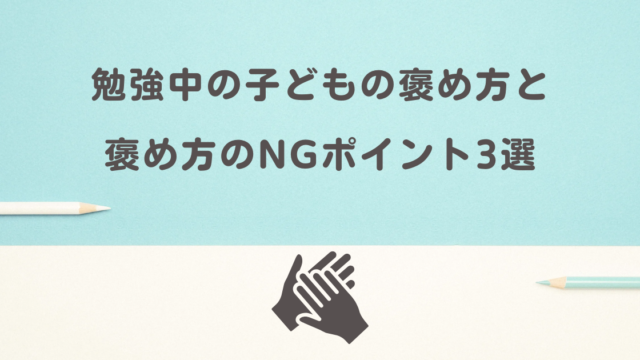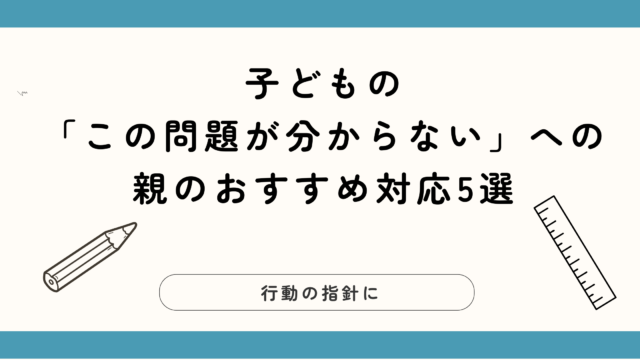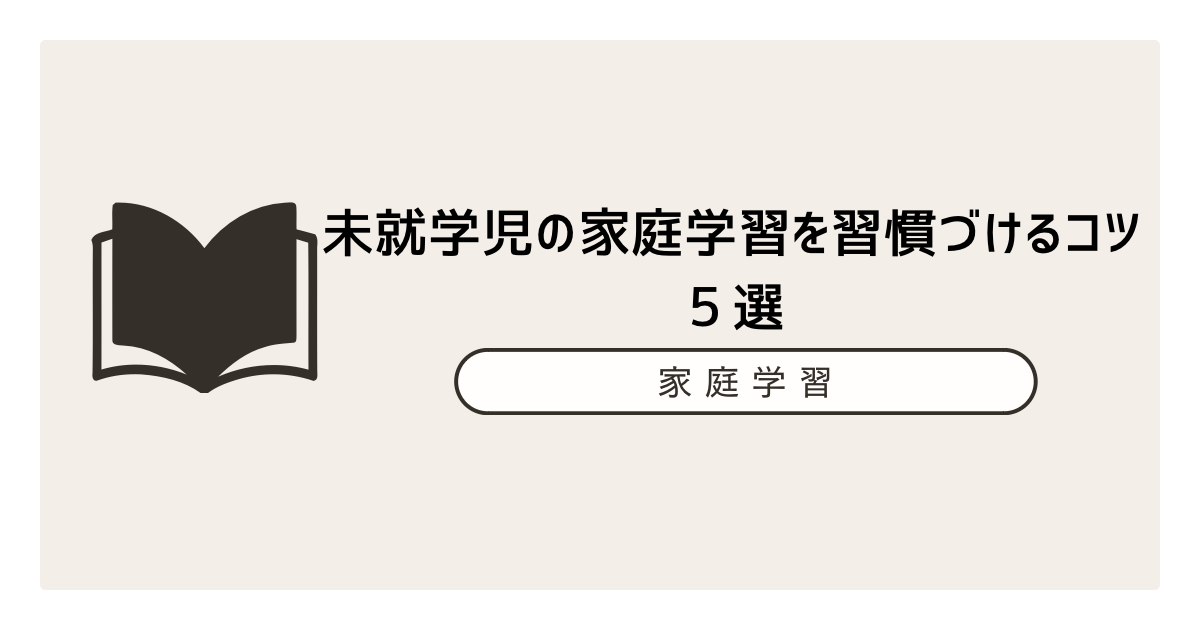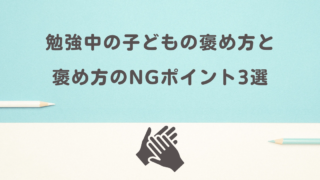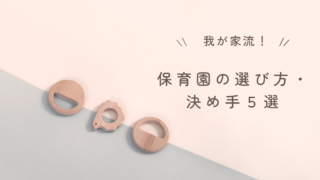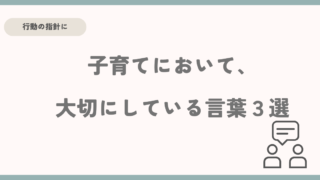子どもに「なんで勉強するの?」と聞かれ、上手に答えられません。
「勉強したほうがテストでいい点数取れるよ」とか「選択肢が増えるよ」とか思いつく理由を並べてみますが、子どもも納得していないように思えますし、私自身もなにかしっくりこない感じはあります。
このような質問を頂きました。
子どもの「なぜ勉強するのか!?」という質問にはドキッとしてしまうこともありますよね。
勉強する理由の解答は三者三様であると思いますが、学習塾運営歴20年の私が考える「勉強する理由」は、
多くの知識をもつことは楽しく生きることができるから、だと考えています。
その理由について詳しく紹介していきます。
勉強する意味を伝え続けたい理由
この記事で、勉強に苦手意識を持ってしまう一つの原因を紹介しました。
小学生になると、勉強にネガティブな感情を持ってしまう子が多いです。
小学生になると、宿題が出て、テストがあり、さらには毎回の授業で小テストがあり、という日常が待っています。
その度にお母さんやお父さんは「宿題やりなさい」、「テスト勉強はしたの?」など、子どもがちゃんと勉強をしているのかを確認することが多くなると思います。
もちろん子どもが小学校低学年で小さいうちは、子どもの勉強に関して、
子ども任せにするだけでなく、親も把握して学校の先生の指示通りできるよう誘導する必要はあります。
ただ、毎日、勉強したかの確認や、小言のようなことばかり言っていても、
子どもも嫌になってしまいますし、親も楽しいわけではありませんよね。
子どもに勉強を前向きに取り組めるために私たち親ができることの一つは
「なぜ勉強するのか、勉強したらどんな❝いいこと❞が起こるのか」を教えることです。
もちろん、即効性のあるやり方ではないですが、
子どもが小さいうちから、一貫性を持って伝え続けると、じわじわと子どもの脳に伝わり、
勉強に対してポジティブな感情を持つことができる、と信じています!!
勉強する意味は、知識を身に付けるもの
「勉強=テストされるもの」と捉えてしまうと、子どもも親も試されているような感じがして嫌なものです。
しかし、「勉強=知識を身に付けるもの」と考えると、日常生活に非常に役立つものとなります。
知識を身に付けると、日常生活が楽しくなる。
私たちが何気なく過ごしている日常生活において、「勉強」で得た知識を使っていることは案外多いです。
例① 買い物
スーパーに行き、原産地は一緒の100グラム100円の豚肉と、200グラム150円の豚肉が売っていました。
安い方を買いたいな、と思ったとき、どちらを買うでしょう?
頭の中で計算がパパっとできれば、きっと200グラム150円の豚肉を購入するでしょう。
お得にお買い物ができました。
例② 季節の食べ物
夏に「桃が美味しい季節だから、桃のレシピを食べたいな」と思い、桃を買いに行く。
夏ならではのワクワクですよね。
例③ 日本の地理
旅行の計画を立てるとき、「どこ行く!?」「何する!?」となったとき、
沖縄の綺麗な海が見たい!北海道の美味しい海鮮が食べたい!など、
日本の地理が分かっていると、自分のしたいことをパッと思い浮かべることができます。
このように、私たちは、学校の勉強として習ったことを、知らず知らずのうちに日常生活に活かして生活しています。
その季節ならではのワクワクも、
本やマンガを読み「面白い」と思う心も、
お得に買い物ができて「ラッキー」と
小さな喜びを感じることも、友達と楽しく過ごすための社会的ルールが身についていることも、全て「勉強」しているからです。
算数で計算の仕方を学び、国語で文字の読み書き、人の気持ちの読み取り、社会で季節や特産品や地方の特徴を習っているからこそ、
感じれる喜び・幸せなのです。
テストはテスト中の緊張感や点数となり残りますが、
日常生活で知識を使っていてもなかなか「勉強してたから、この小さな喜び感じれてるーー」とはなりにくいため、見落としやすい観点となりますね。
知識豊富な人ほど多角的な視点を持っており問題解決能力が高い
勉強でも、仕事でも「トライアンドエラー」はつきものです。
トライアンドエラーを繰り返しながら、上達していくものです。
問題解決するためには解決方法を提示できなければなりませんが、
解決方法を一つしか思いつかない人と、十個以上思いつく人でしたら、どちらの人の方が問題解決できるでしょう。
もちろん後者の問題解決方法を十個以上思いつく人ですよね。
解決方法を思いつくかどうかは、知識の量で差がつきます。
もし解決方法が一つしか思いつかなければ、その解決方法を試し、
失敗に終わった場合、その後太刀打ちできず諦めるしかできなくなります。
解決方法①を試し、失敗したら、次解決方法②はどうだろう!?
それでもダメなら、解決方法①のこの部分と、解決方法②のこの部分を組み合わせるのはどうだろう!?と、トライアンドエラーができます。
またこの上記の仮定で、仮説を立てる力、分析する力がついてくるため、さらに能力は向上します。
この繰り返しで「多角的な視点」が育っていくと、考えています。
例えば、あなたが女性だとして彼氏とキャンプにきてテントを立てます、となったとき、
説明書通りの工程を踏んだとしても、テントが上手に立たなかったとします。
テント立てるの無理だ!難しい!仕方ないから、今日は車で寝よう。
と言われたら頼りないですし、嫌ですよね。(というより、ドン引きできよね。)
風向きの関係でここはテントが立てられないみたいだから、こっちの方角に変えて立ててみようか。
それでもダメなら、テントの立て方をYouTubeで調べてみようか。
テントを立てられるように、様々な解決策や工夫をしてくれる人が頼りがいがあり、
こういう旅行やアウトドアならではのアクシデントも楽しめます。
知識豊富な人ほど、アクシデントも楽しめそうです!
また日常生活では、何か小さな困難って意外に多くあります。
給湯器が壊れた、とか、スマホをなくした、とか。
そういうときにとっさに機転をきかせれるか、どうかで日常生活のストレス度合いも変わってくるのではないかと思います。
知識豊富な人ほど、将来の選択肢が多く、したいこと・なりたいものになれる!
学歴が高いほど、将来の仕事の選択肢が多い、とよく言いますが、もちろん正しいと思います!
しかし「学歴が高い方がいい」というだけでは、夢がないというか、希望がないというか、少し冷たい感じがします。
私、個人的には、知識が多いほど、将来の仕事の種類も知る機会も多いでしょうし、
また調べ方も分かっていると思います。
細かい職種や仕事内容を分かっていた方が自分の本当にしたいこと、なりたいものに近づけます。
例えば、「ユーチューバーって稼げそうでいいな」と思ったとします。
以下、イメージです。
(※知識が乏しい人はこう!豊富な人はこう!という決めつけではありません。あくまでイメージです。)
知識が乏しい人は、「ユーチューバー なり方」と調べて、ユーチューバーがいかに大変かを知ります。
「ユーチューバーって休みないんだ、大変だ。私には無理だな」と思い諦めてしまうかもしれません。
知識豊富な人は、まずユーチューバーには、表に出てる人・出てない人がいることを感じ取ります。
そこで「ユーチューバー 仕事内容」と調べ、ユーチューバーには、演者・台本を書いている人・編集している人、等、
一つの番組が出来上がるまでに多くの人が関わっていることを知ります。
その中で「私は動画の編集をしたいな」と思ったとしたら、動画編集を行うためには、どういう道を選べばいいのか、本当に動画編集1本に絞っていいのか、等、考えながら、
または親御さんと相談しながら、自分の将来の道をより具体的に決めていけるのです。
知識豊富な人は、何か物事があったときに、それに付随する関連知識を多く持っているため、より具体的に詳細に考えることができます。
まとめ
以上、勉強をする意味・目的でした。皆様の何か参考になれば嬉しいです!
本来は、勉強して知らない世界を知ることや、分からないことを理解できることは楽しいことなはずです。
テストのように、日常生活で、私たちが何気なくしていることを「今、これ、勉強している成果だよー!」と、逐一教えてくれるシステムがあれば、勉強に対するモチベーションが上がる気がするんですけどね。
自分で見つけていくのは、子どもはなかなか難しいので、大人が寄り添って、勉強をする意味を伝え続けてあげたいものです。